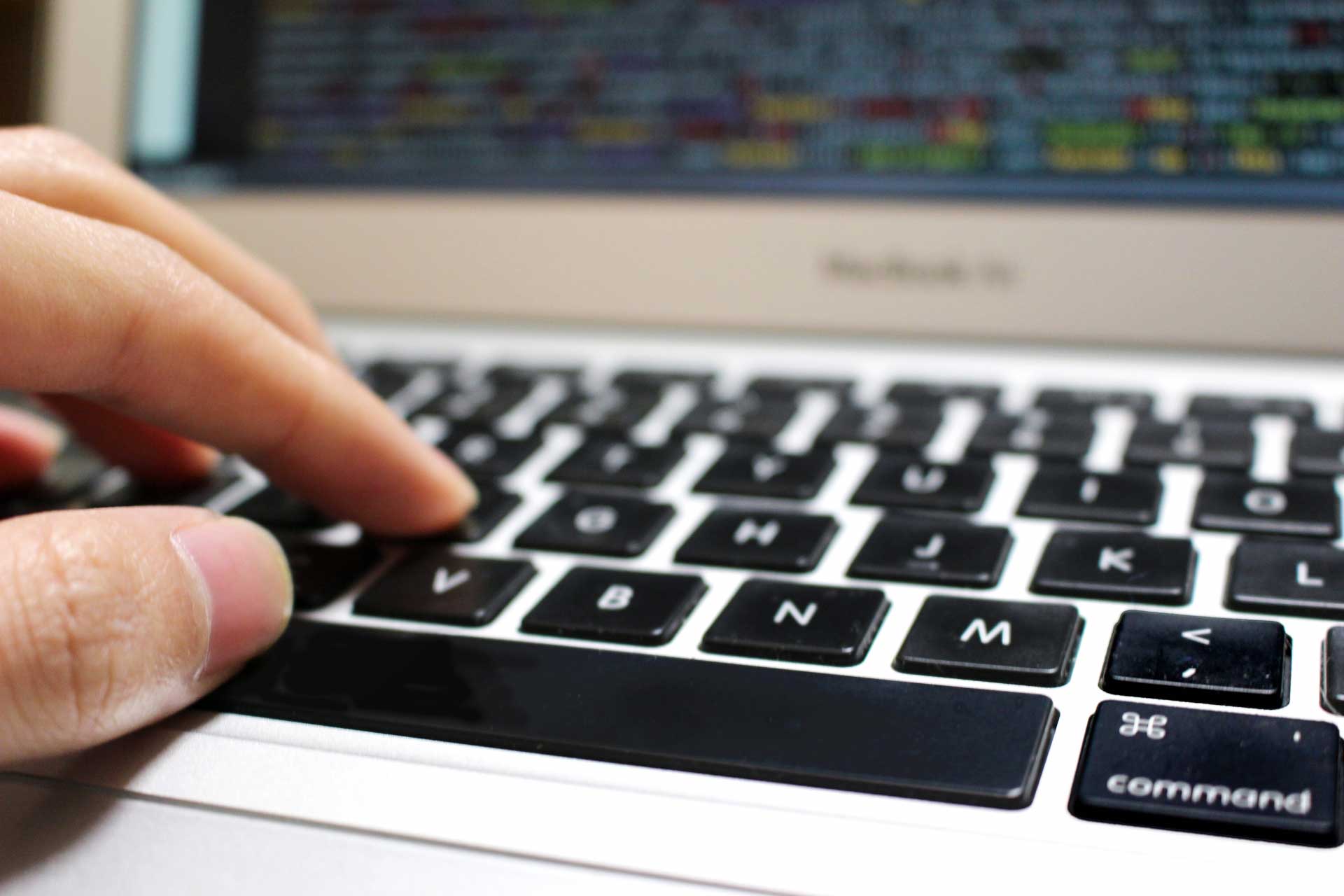動産とは、パソコンやテレビ、所有している車、他にもペットやコレクション、また腕時計や宝石やアクセサリーなどです。
相続による動産の名義変更は、法務局での登記手続きで完了する不動産の名義変更とは少し違います。
中でも車の名義変更は収集するべき書類も多く存在しますので、名義変更を個人で行うことも可能ですが、それなりに時間と手間がかかる手続きです。名義変更を行わないでそのままにしていれば、売買を行うことが出来なくなります。
また車や所有している貴金属などは、時期によって価額の差が生じ、安くなったり高くなったりしますので、なるべく早く名義変更を行いましょう。
価値のある動産への対応
遺言書が見つかったときは、動産におけるコレクションや価値のある財産をどのようにするのかも確認しておきましょう。例えば切手のコレクションのように、何年にもわたって被相続人が収集し、価値が高くなっている動産もあります。また、宝石などの動産も鑑定を行う必要があります。
動産の相続の際の料金
動産の状態によって料金が変わることがあります。
鑑定料金や相談料などがかかる専門家もいますが、名義変更をしっかり間違いなく行うことが大前提です。
遺言書が存在する時には、遺言書が十分な効力を発揮してくれます。
被相続人が残した動産にどのようなものがあるのかを確認し、把握することが必要です。無記名債権も動産とみなされますので、細かい備品まで遺産分割協議を行い、誰がどの動産を相続するのかをしっかり決めることが大切です。
相続後に動産が原因でトラブルになる事もあります。
そのため動産に関しても皆さんで分割協議を行い、後のトラブル回避を行いましょう。
特に車や貴金属などの財産は高価な財産になりますので、どのように分割をするのか、専門家に相談することも大切です。
相談予約はこちらから