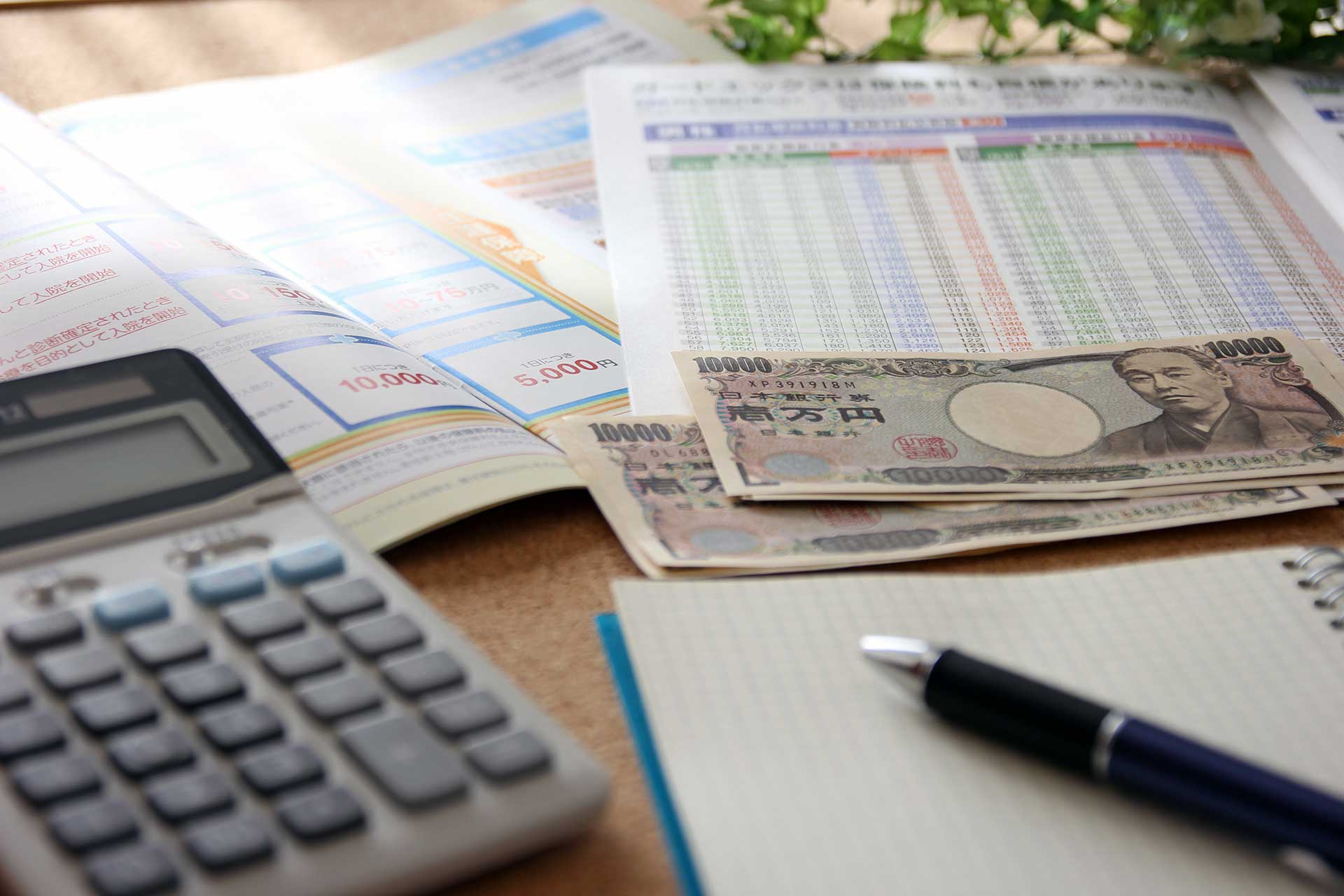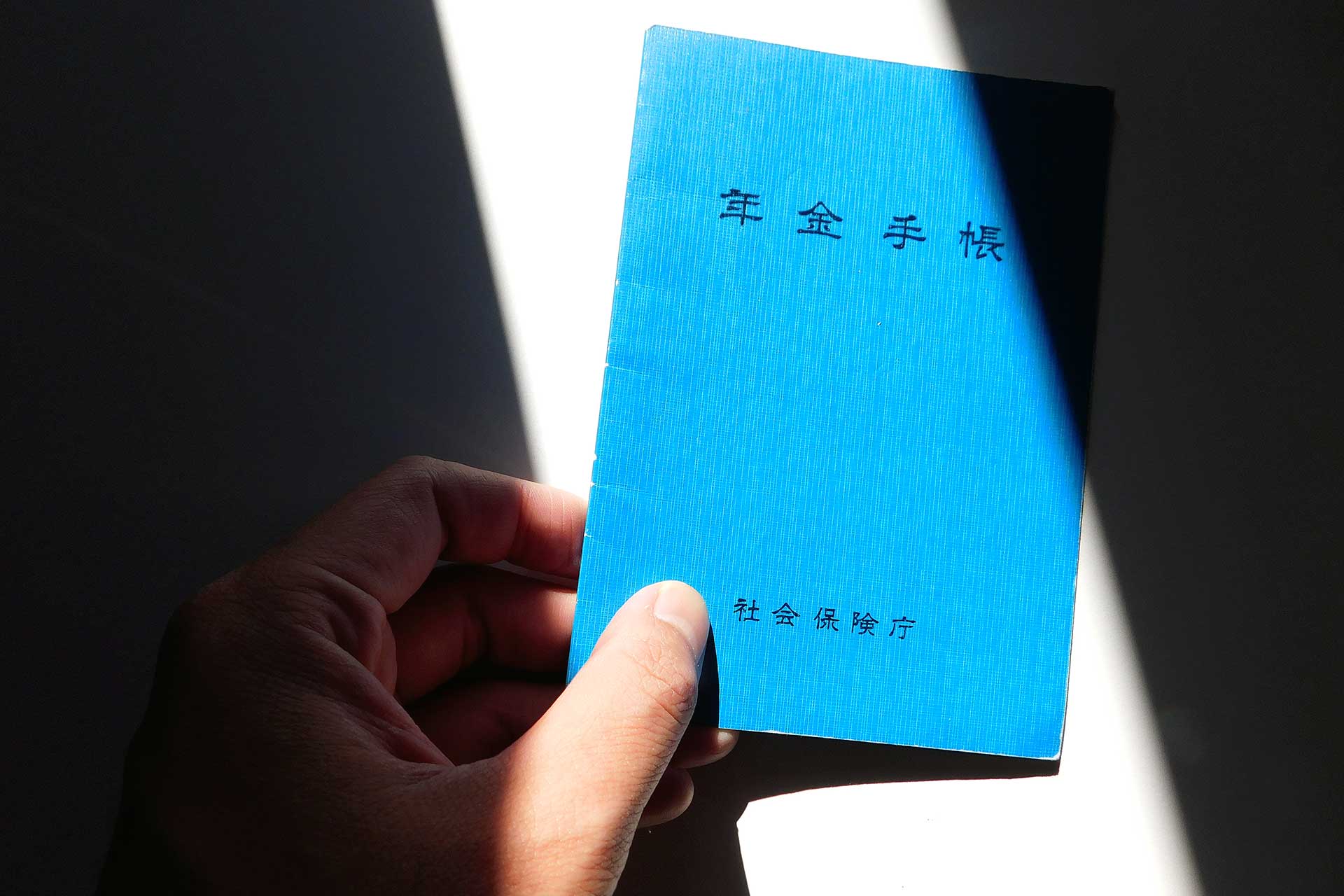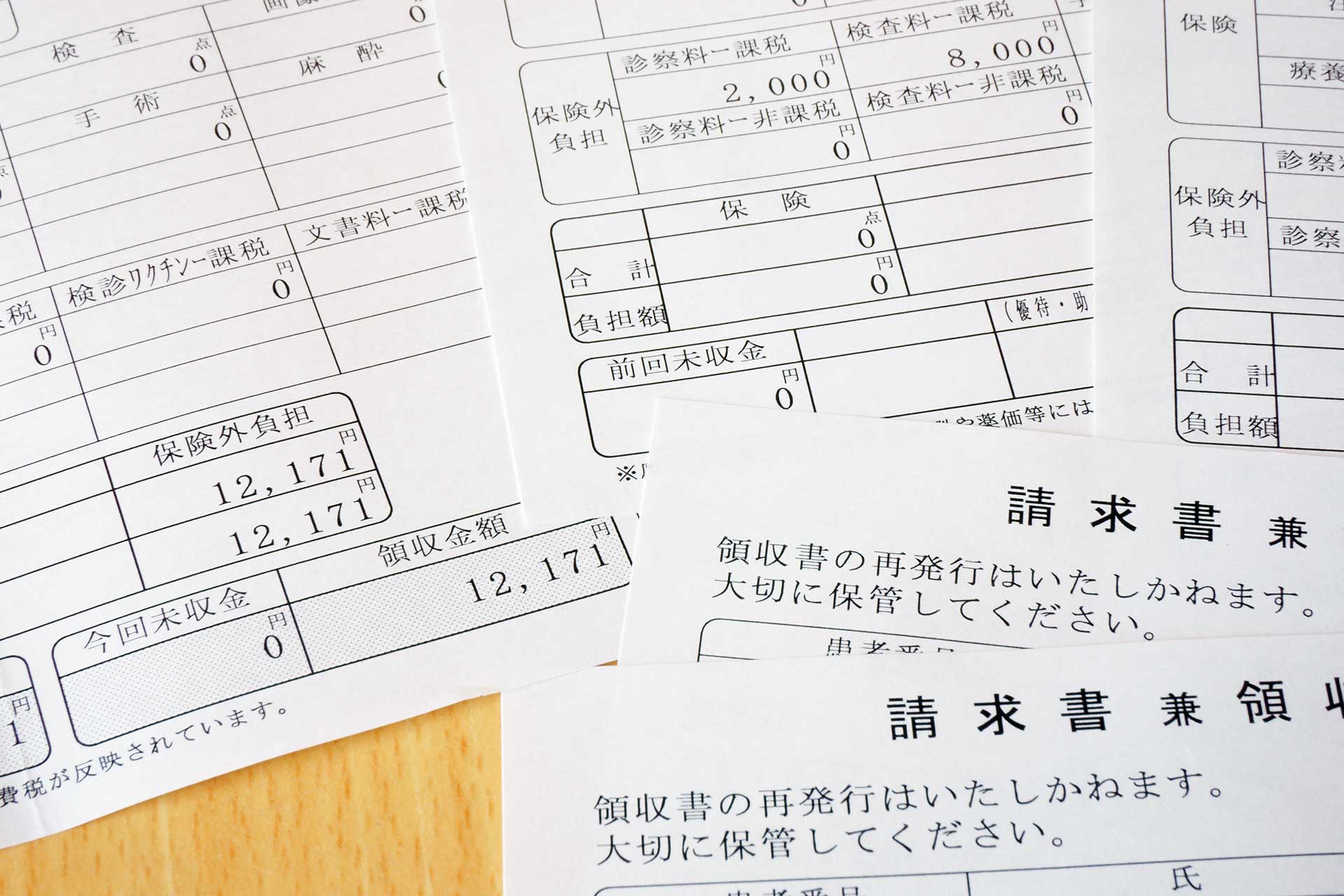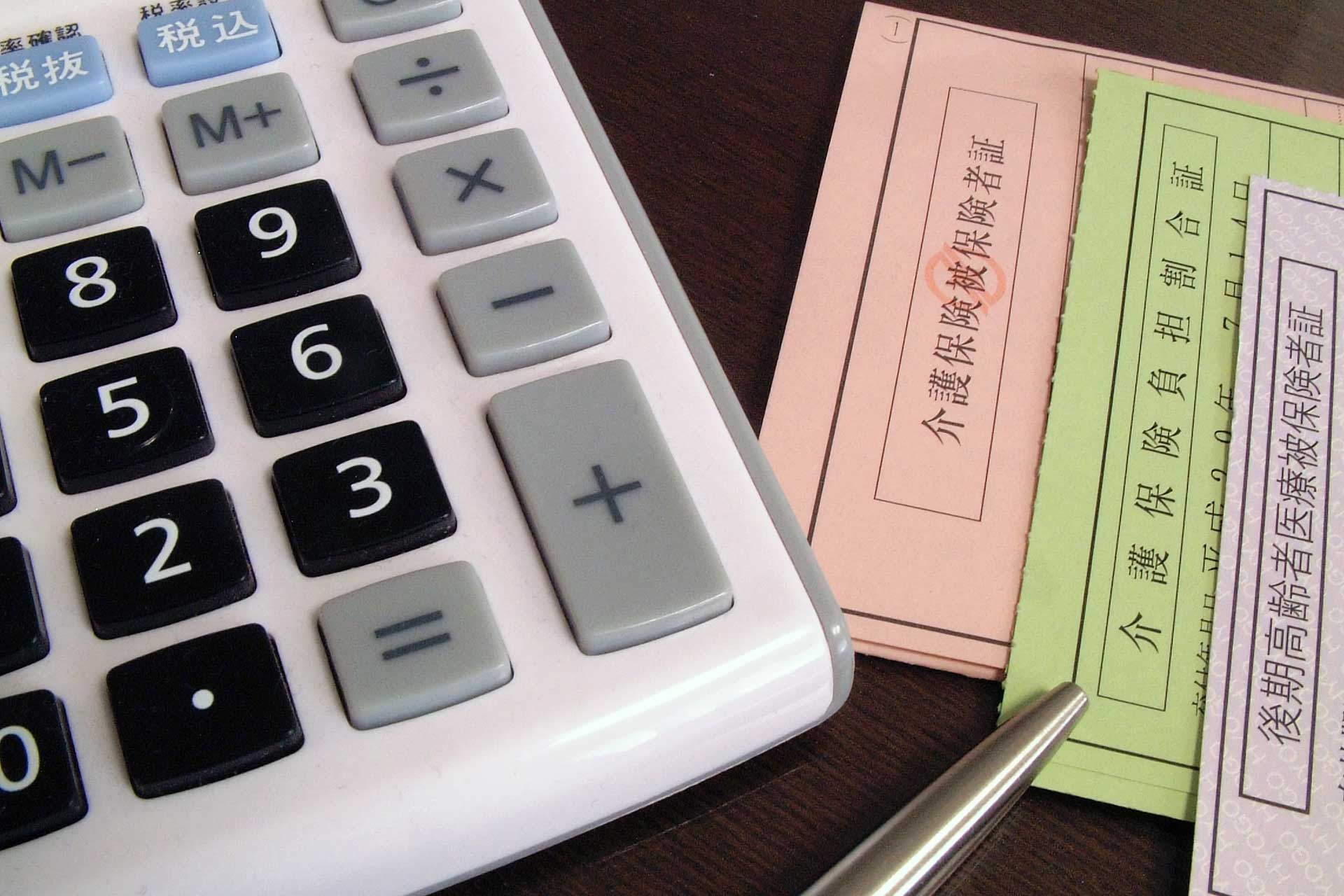遺産分割において不動産の共有は避けた方がいいと言われています。
共有名義の土地の相続について知っておきたい問題点と、共有に適してるケースについて解説します。
共有名義の土地の基礎知識
共有とはひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。
共有の場合、各共有者は持分の割合に応じて共有物の全体を使用することができます。
極端な例ですが、土地について各自の持分が100分の1と100分の99だとしても、それぞれの共有持分は土地全体に及ぶので利用方法に違いはありません。持分が100分の1だから共有土地の100分の1の部分だけしか使えない、などということにはなりません。
共有土地を賃貸して賃料収入があるような場合には、各共有者が共有持分割合相当の賃料を得る権利があります。税務上の所得税の確定申告でも共有割合(持ち分割合)に応じて不動産(賃料)収入の申告を行います。
共有物の管理は持分の価格に従いその過半数で決めるものとされていますので、共有持分に応じて発言権が異なることとなります。
共有物の状態を変更したり、処分するなどの際には、共有者全員の同意が必要です。
動産でも共有状態が生じることはありえますが、実際に問題となるのは不動産の共有が圧倒的多数です。不動産の共有状態は相続によって発生するほか、例えば、土地を夫婦名義に変更するなどのケースが考えられます。
不動産の所有状態は不動産登記において公示されています。(登記事項証証明書に記載される。)共有の登記がされていれば容易に判別することができます。相続などで登記が元のままになっていたりすると、登記簿を見ても現在の所有関係は分かりません。
共有のもたらす問題点
共有名義の土地は相続にあたって様々な問題が生じる可能性があります。
共有持分のさらなる細分化
土地を2分の1ずつ共有している共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。土地の共有者が増えるという事は利害関係人が増えるという事で、土地売却時や土地活用したいときに全員の意見がまとまらないという問題が度々発生します。
遺産分割を行うことが困難になる
共有関係を解消して単独所有とするためには、共有者全員で遺産分割協議(共有物分割協議)を行います。共有関係が複雑化した場合、共有者の中に協議に非協力的な持分権者が生じる可能性があります。特に、共同相続人の中に「故人の前配偶者の子」など、普段付き合いのない人が含まれているような場合、意思疎通が困難になります。
共有関係を可能な限り早いうちに解消することや、遺言書により将来問題が生じないように対処をしておく事が重要です。
平等に相続したいとの思いから、不動産も含めて全てを法定相続分割合で分割するケースがありますが、このような遺産分割は避けたほうがいいでしょう。
相続時点で相続人間が円満であっても、その内の誰かが亡くなり、次に相続人となる人との間も上手くいくという保証はありません。遺産分割の時点から先の相続まで見据え、分割方法を考えることが大切です。
共有状態の解消についての公的制度
共有名義の土地を相続して相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割に代わる処分を求めることが可能です。司法書士・弁護士などに相談することとなり、余計な手間や高額な報酬が生じるおそれがあります。
共有状態は相続開始前に解消しておく方が望ましく、遺言で将来の共有状態解消を目指すことをお勧めします。
共有による遺産分割が適してるケース
田中さん一家は父が亡くなり、子供3名で遺産をどのように分割するかの話し合いをしていました。父の遺産は自宅(3,000万円相当)と僅かな預貯金のみです。三人の子供で遺産分割後に自宅を売却して金銭で分配することを話し合い、自宅を三人の共有(一時的に一人の名義にしても可能)にした後に売却して、各自が1,000万円ずつ受け取りました。
遺産の大半が不動産で平等に遺産分割することが難しい場合、売却を前提とした遺産分割、換価分割をすることができます。すぐに売却することに共有者全員が同意しているため、共有のデメリットを受けることなくスムーズな遺産分割が可能となります。
相談予約はこちらから