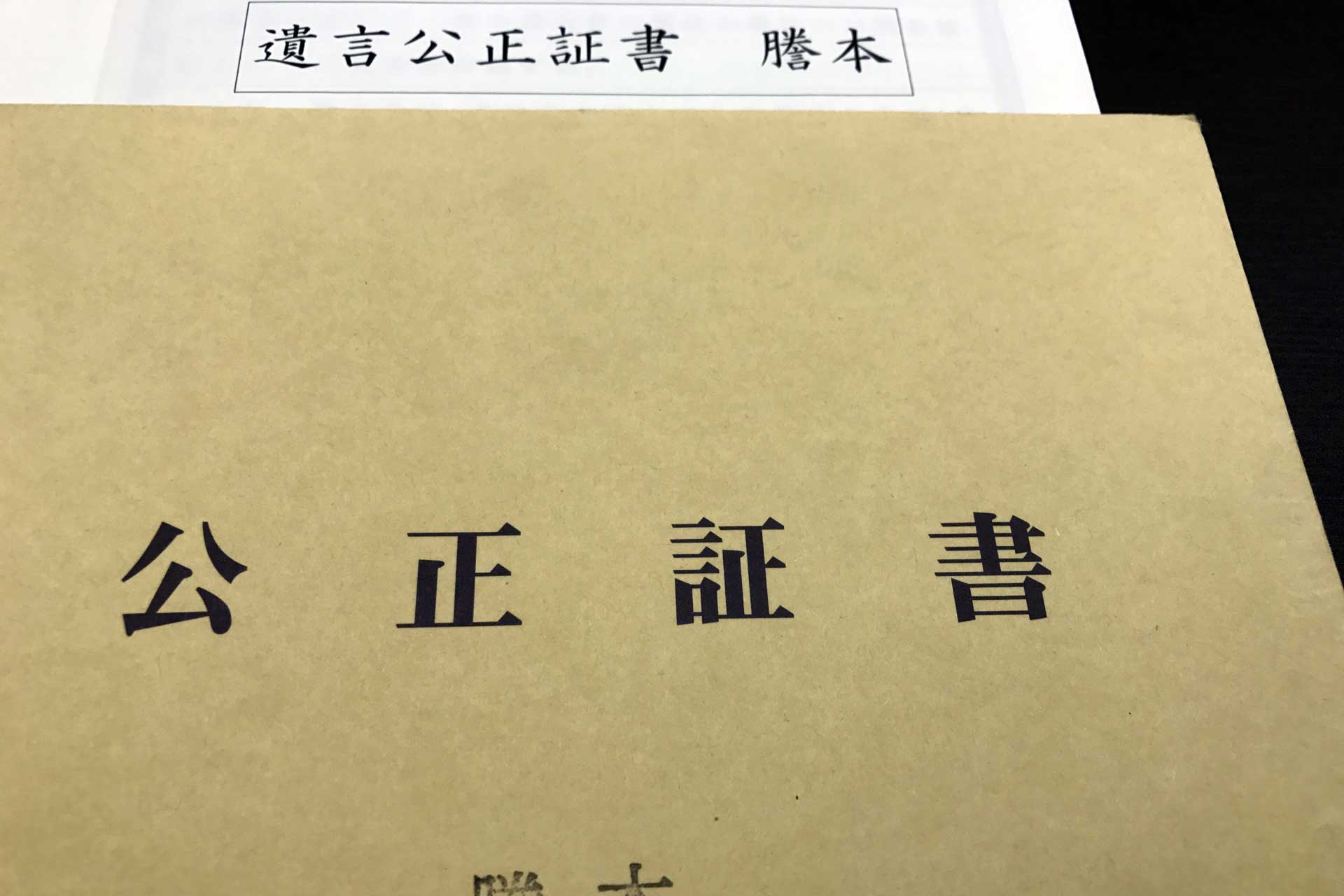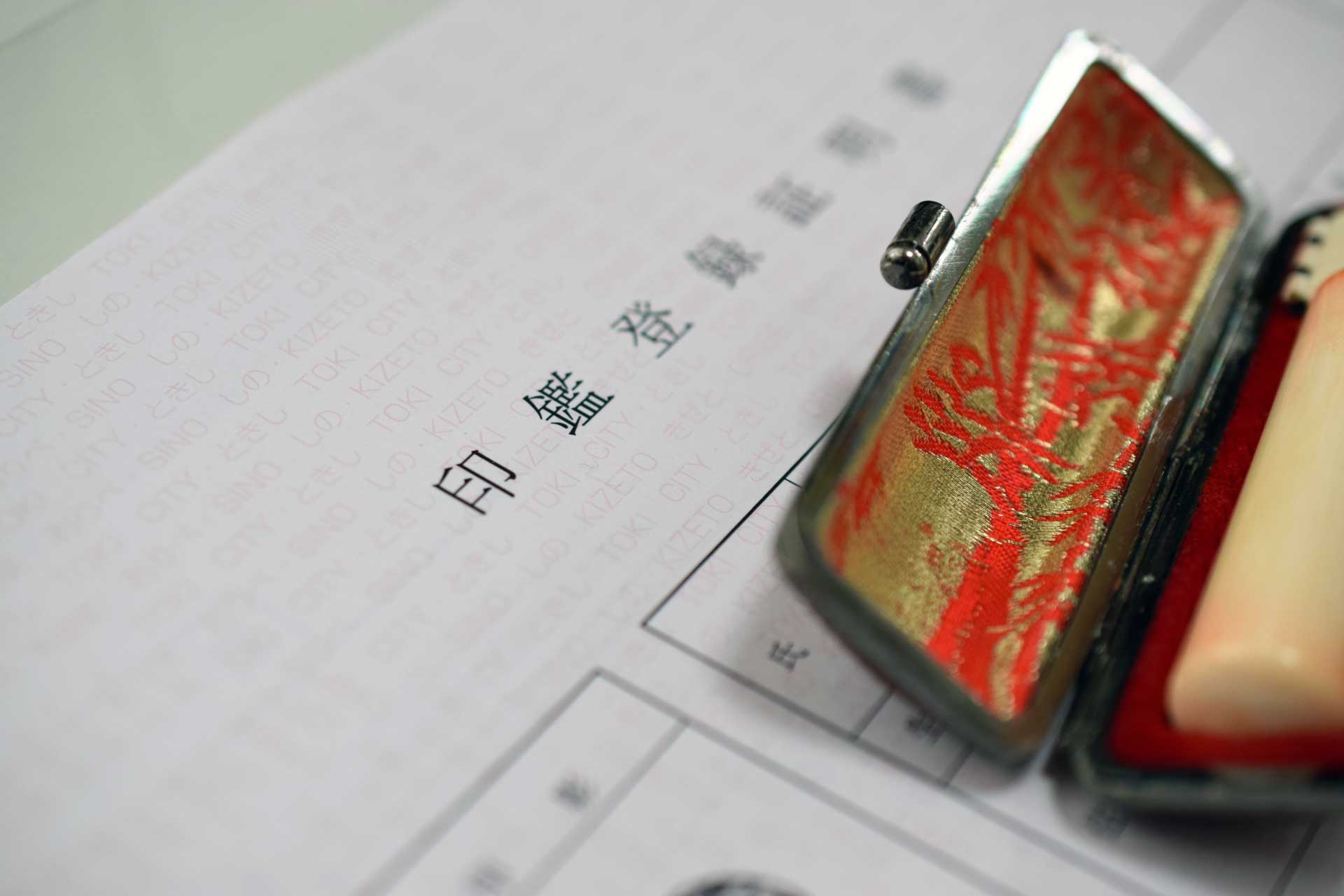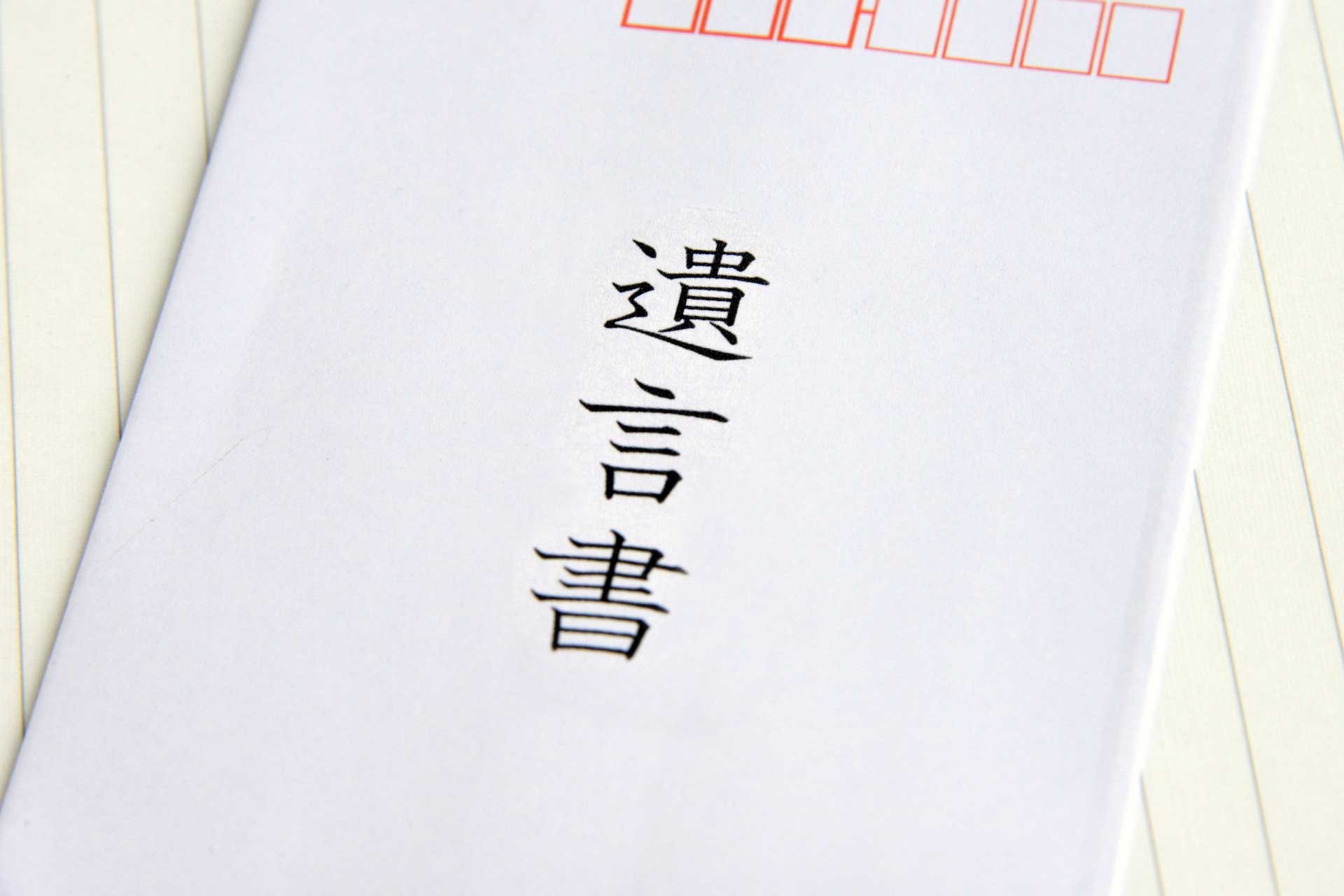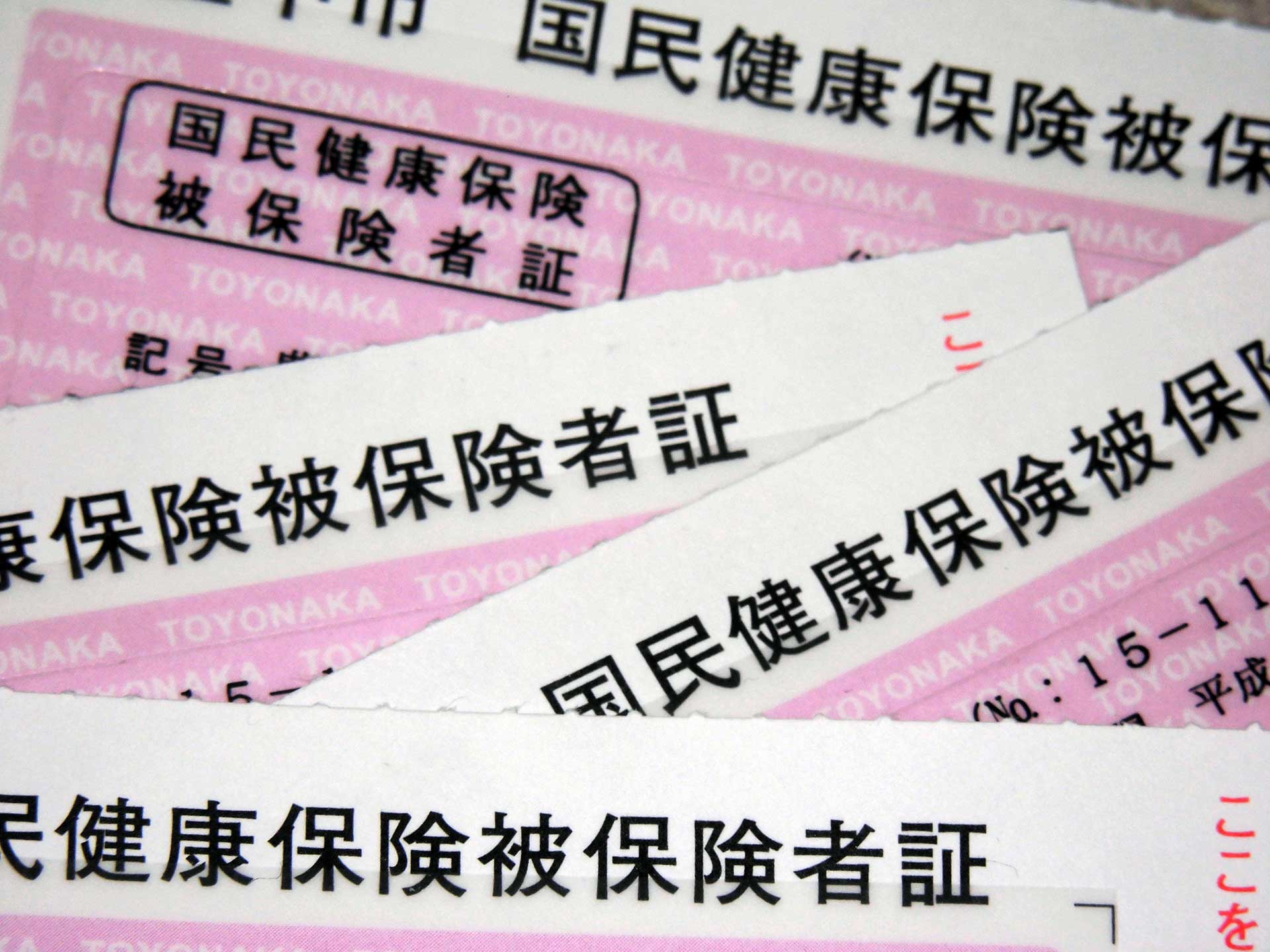会社の規模や業績等に応じた対策
非上場株式会社の事業承継といっても、資産規模が数千万円の企業から数百億円の企業まで千差万別です。
事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)
事業承継税制の効果は、会社の資産規模が大きく、収益力が強くなればなるほど増大します。
逆に、資産規模が小さく従業員の数も少なければ、事業承継税制を使わずに非上場会社の特色を活かした対策が功を奏します。
家族経営の同族会社
家族経営の同族会社の事業承継対策のチェック事項は次のとおりです。
- オーナーの所有する不動産と法人所有不動産が峻別されているか
(法人不動産と個人不動産の調整) - 代表者など親族から会社が借り入れているお金の使途
- オーナーの自宅は社宅か
(自宅の小規模宅地特例の検討) - 会社の本社、営業所、倉庫、工場などは誰の所有か
(事業用不動産の小規模宅地特例の検討)
ご用意いただく資料
- 会社の過去5年分の法人税の申告書
- 株主名簿
- 法人所有土地の固定資産税課税通知書
- 法人所有有価証券の明細
- 会長、社長などご親族の所得税の申告書過去5年分
事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)の検討
経済産業省が奨励する事業承継税制は、自社株式に係る相続税を80%も節税できる特例です。
収益力が高ければ高いほど事業承継税制のメリットがありますので、申告所得が数億以上ある事業体を経営されていらっしゃる方が事業承継をお考えの場合、事業承継税制を検討するべきです。
税理士法人日本税務総研では「中小企業といいながら実質的に大規模な会社」の事業承継税制を実施しています。
専門の税理士が細部に渡ってご説明いたしますので、是非ご相談ください。
非上場株式の相続税評価
株式の評価と対策の構築は、理論と経験がものをいう業務です。
自社株の評価と相続税対策をご検討の方はぜひご連絡ください。専門の税理士がご対応致します。
取引相場のない株式の相続税評価は以下の観点から行います。
- 納税義務者が同族株主等に該当するか
- 評価会社が一般的な会社に該当するか
- 業種に応じた規模は大中小のどれか
- 業態や保有資産の偏りから見て特定の会社として評価しなければならないか
- 配当還元方式で評価すれば足りるのか
多くの場合、会社所有の不動産や有価証券の評価も必要です。
株主構成を変えることで、評価方法が大きく変化することもあります。
金融機関からの提案のチェック
事業承継計画は、会社の事業計画に則して、会社の支配権の承継計画とそれに付随する相続税の納税計画が中心となるべき
税理士法人日本税務総研は、税理士ならではの会社創設から現在までの社歴をも考慮したご提案を心がけています。
近年、銀行や証券会社といった金融機関から事業承継の提案を受ける企業が増えており、提案の狙いやメリット、デメリットを中立的な立場から説明してほしいとのご要望を受け賜ることが増えています。
金融機関の提案は、法人税の申告書、決算書、株主名簿に依存する提案です。
借入金で資産を購入し株価を下げたり、定款を変更して議決権のない株式を作りましょう、というようなものが多く見受けられます。
金融機関からの提案に少しでも疑問を感じられた方は、ぜひ一度ご連絡ください。
会社の顧問税理士とプロジェクトチームを組むことも可能です
顧問税理士は法人税と消費税の観点から長年会社の決算を見ているので、相続税の観点からみると非常に不利な形となっているケースが珍しくありません。
次のテストをしてみてください。
□ オーナー(56)の母(80)に年間数百万円の役員報酬を支払っている
□ オーナーの母からの借入金が1,000万円以上ある
□ オーナーの母の居住している家屋は会社名義である(社宅)
ひとつでも当てはまるようなら対策を打つ必要があります!
税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は会社の顧問税理士とプロジェクトチームを組んで、貴社の事業承継の提案を行うことも可能です。
ぜひ一度ご相談ください。
相談予約はこちらから