よろこんでお引き受けします。法人や所得は従来どおりご継続ください。
法人税を専門とする税理士事務所の中には、相続税の申告書の作成はしたくないという方もいるのです。
専門外のことでなにかあって、従来からの顧問先を失うことは避けたいと考える方もいるそうです。
相談予約はこちらから

よろこんでお引き受けします。法人や所得は従来どおりご継続ください。
法人税を専門とする税理士事務所の中には、相続税の申告書の作成はしたくないという方もいるのです。
専門外のことでなにかあって、従来からの顧問先を失うことは避けたいと考える方もいるそうです。
相談予約はこちらから

最近、生まれた時から海外にお住まいで日本語を話せない相続人や受贈者が増えています。
被相続人・遺贈者・贈与者、相続人・受遺者・受贈者の全員が日本国内に住んでいなくても、日本国内の財産を相続すると我が国の相続税が課税されます。この時、被相続人・遺贈者・贈与者、相続人・受遺者・受贈者のいずれかが過去10年以内に日本に住所があれば、全世界課税とされます。
相続税の申告期限は、亡くなられたことを相続人・受贈者が知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。海外居住相続人・受遺者も同様です。海外に推定相続人である子どもや孫がいる方は、いざというときにあわてないように、事前の準備をお勧めします。
税理士法人日本税務総研は、海外に所在する財産評価をお受けしています。米国には提携事務所を有し、ベトナム、シンガポールなどにも提携先を有しています。英語を話すスタッフも常駐しております。お気軽にご相談下さい。
課税時期に納税義務者である相続人・受遺者又は受贈者が日本国内に居住していれば、財産の所在を問わず我が国の相続税法が適用されます。
海外に移住なさる場合の出国に伴う所得税の申告などお手伝い致します。有価証券を所有されている方はいわゆる出国税が課税されるおそれがあります。思わぬ税負担が生じないためにも、移住計画を練っていらしゃる時点で早期にご相談ください。
国外財産調書は海外の財産の評価を行う必要があります。資産税の知識のある事務所に依頼することがスムーズな選択です。
法人税や所得税の申告と合わせてお受けいたします。
税理士法人日本税務総研では、国外財産調書の提出のお手伝いに加え、必要に応じ、相続や相続税対策アドバイザリー業務を受け賜ります。
その年の12月31日において、総額5,000万円を超える国外財産を有する人は、国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。
海外に相続人がいらっしゃる場合は、財産の多寡にかかわらず基本プランの報酬を受け賜ります。
我が国の相続税申告と合わせて海外での税務申告が必要になる場合、提携海外事務所又は大手弁護士法人と共同してご対応致します。
(外国の税務申告は外国の法律事務所又は会計事務所が行います。)
気長な租税回避の方法
相談予約はこちらから

もちろん可能です。
税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。
1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。
納税額も多額に至るため、申告書の作成に合わせ納税計画も早期に作成する必要があります。
遺言で数十億円の寄付がなされるケースもあります。土地や株式など含み益のある資産を法人に遺贈すると、原則として、被相続人に譲渡所得が生じ、相続人が納税義務を承継することになります。公益法人等に遺言で寄付する場合、譲渡所得の非課税申請(措置法40条)の準備も必要です。
高額の遺産の申告は、物納準備にも時間がかかります。早めにご相談くださるようお願い致します。
相談予約はこちらから
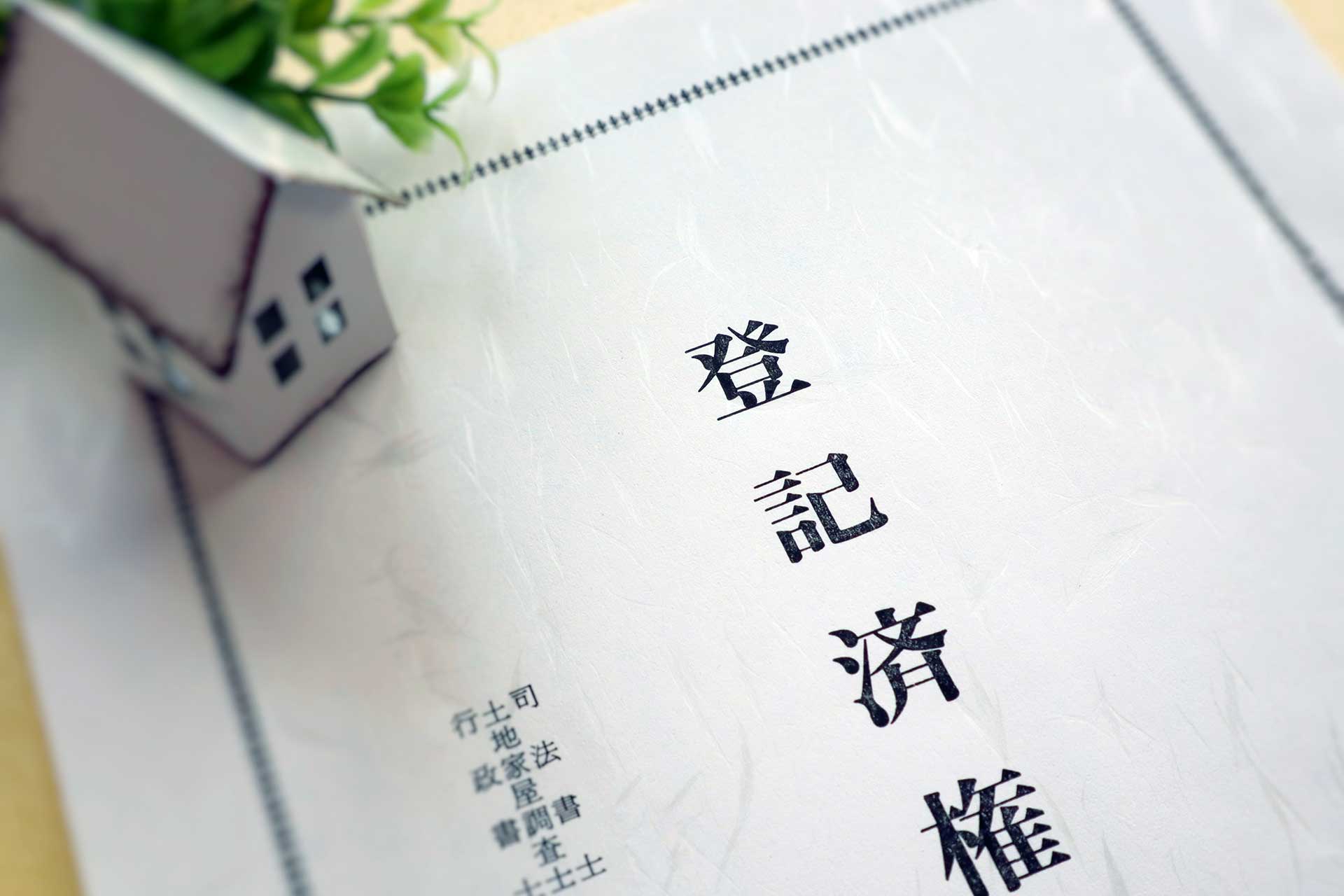
民法549条によると『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約』と規定されています。
つまり、あげましょう、もらいましょうという贈与者と受贈者との意思で成立するものです。
相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。
ただし、名義人となった人が自分が名義人となっている事実を知らなかった場合、名義人となった人がこれらの財産を管理運用などを事実上していない場合などには贈与には当たらないとされています。
相談予約はこちらから

平成17年の創設以来、累計3,000件を超える相続税申告書作成および申告代理業務を行っています。
当事務所所属、ベテランの税理士の(国税がチェックするポイントを押さえた)ヒヤリングをお試しください。
相談予約はこちらから

未成年の相続人が下記(1)~(3)のすべてに該当する場合には、相続税の税額控除を受けることができます。
(20歳 ― 相続開始時の年齢)× 10万円
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
相談予約はこちらから

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
相続開始時に以下の3つすべてに該当する者
控除額は次の算式により計算した金額です。
一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円
障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないときは、引ききれない部分の金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
相談予約はこちらから

我が国の民法は、共同生活を行う夫婦でも、片方の名義で得た財産は片方の固有財産であるとされています。サラリーマンである夫が働いて得た給料は夫の財産だということです。夫婦が離婚すると離婚に伴う財産分与は基本的に夫名義の財産の1/2です。夫の名義の財産について、妻が潜在的な共有持分を有しているというのがその理由です。
相続税の世界では、配偶者が取得することが確定した遺産については、法定相続分または1億6千万円までは税額控除を受けることができます。
何らかの理由で(必ずしも相続争いがあるからとは限りません)、申告時までに分割できない場合には、配偶者の税額軽減を受けることはできません。
相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
相談予約はこちらから

隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。
被相続人がその隠し子を認知しているなら、その隠し子は相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなり得ません。
本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。
認知をしていた場合は戸籍に記載されますので、被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って集めれば判明します。
隠し子であっても本来相続人である者を除いてなされた遺産分割協議は無効なものとなります。後日、隠し子から遺産分割のやり直しを請求された場合は遺産分割のやり直しをしなければなりません。
隠し子の存在が疑われる場合はしっかりと相続人調査をおこなった上で遺産分割協議を進めるべきです。
相続が開始した後に相続人としての地位を手にいれた隠し子の場合は、既に終わっている遺産分割のやり直しを請求することは出来ず、自己の相続分に応じた価額を請求できるにとどまります。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子の相続分と隠し子(以下、非嫡出子)の相続分が同等となりました。
法律の改正を知らないと相続人間で無駄な争いを起こすことになりますのでご注意ください。
相談予約はこちらから
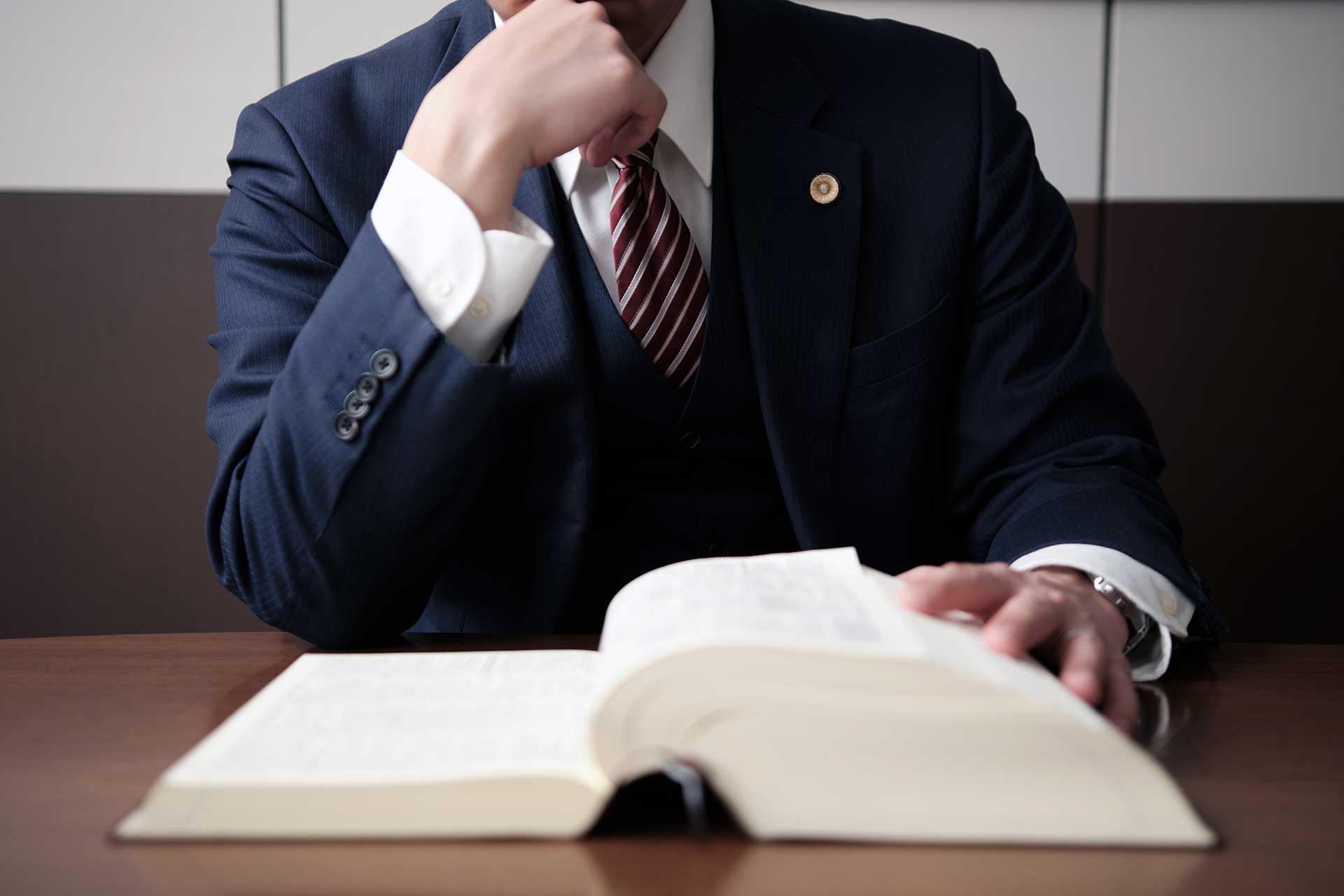
当事務所は、相続税の申告業務に不慣れな専門家(弁護士・公認会計士・税理士)のご依頼に応じ、相続税の申告書作成支援業務も行なっています。
国税局で相続税の調査を担当していた経験豊かな税理士が申告業務をお手伝いします。
特に遺産総額が3億円を超える相続税の申告書作成業務は、税率も上がってきますし、加算税や延滞税も多額になる可能性があります。ぜひご相談ください。
弊事務所の資産税担当税理士が直接お客様と申告書作成に必要なヒヤリングを行い申告書を作成します。
貴事務所が主体となって申告書の作成を行う場合、弊事務所の資産税担当税理士が初回ヒヤリングから資料収集、評価、申告書の作成まで貴事務所の担当者に同席し、逐次アドバイスを行います。相続税申告書作成のノウハウを習得なさりたい事務所におすすめのプランです。
遺産に係る土地、取引相場の無い株式、外国債券などの評価に自信がないという場合に最適なプランです。
財産評価に特化してお引き受けします。
絶対に間違いのないよう、もう一度チェックしましょう。
Check once more to be absolutely sure.
貴事務所が作成された相続税申告書をダブルチェックします。
当事務所のダブルチェッカー(ダブルチェック専門の税理士たち:国税局で30年以上調査審理を担当していた税理士たち)が税務署が行う申告書のチェックとほぼ同様のチェックを行います。
弊事務所がお客様をご紹介いただき申告書を作成する場合、弊事務所がお客様からいただく報酬の1割をお支払致します。
基本報酬
(表示の金額は最低報酬額を表示しています。最初のヒヤリングでお見積もりいたします。初回ヒヤリングは料金をいただいておりません。
| 遺産額 | 料金 |
| 7,000万円未満 | 38万円~ |
| 2億円未満 | 遺産総額×0.5%+難易度 |
| 5億円未満 | 遺産総額×0.6%+難易度 |
| 10億円未満 | 遺産総額×0.7%+難易度 |
| 10億円以上 | 遺産総額×0.8%+難易度 |
相続税の申告書を作成するためには、申告すべき財産債務と申告する必要のない財産や控除できない債務の峻別及び不足のない資料収集が重要です。
また、被相続人の過去の金融取引に係る入出金の分析も(ご依頼があれば相続人の口座取引と共に)重要な作業です。
これらの作業は、ベテランの税理士のヒヤリングを受けることにより始まり、税務調査に対する堅固な申告書が作成されます。
ぜひベテランの税理士によるヒヤリングをご体験くださったうえで、ご納得いただける報酬を決定してください。
貴事務所が主体となって申告書の作成を行い、弊事務所の資産税担当税理士が初回ヒヤリングから申告書完成までアドバイスを行う場合、貴事務所が受領される報酬の五割を受け賜ります。
| 報酬額 | 30万円~(税抜) |
三社以上株式の持ち合いをしている場合など複雑な評価に困っていらっしゃる方、是非、ご相談ください。
| タイムチャージ | 延べ稼働時間 |
| 2万円 / 時間 (税抜) |
ご質問のケースでは、最初に土地家屋調査士依頼し境界確認を行います。複数の貸地が混在する場所は、貸先ごとに賃貸範囲の境界を確認・設定して測量図を作成します。
土地家屋調査士を入れるまでもない場合は税理士が簡易測量を行います。
複雑な評価対象地は、早期にご相談くださるようお願いします。
まずは、お気軽にお電話もしくはメールでご連絡下さい。
初回打合せ後、現地を拝見し評価手続きをご説明します。
報酬の積算はタイムチャージです。初回打ち合わせで所要時間のおおよそのお見積りをご提示します。
相続税案件の具体的なご相談の連絡窓口
TEL:0120-339-336
Email: inquiry@tax365management.com
相談予約はこちらから