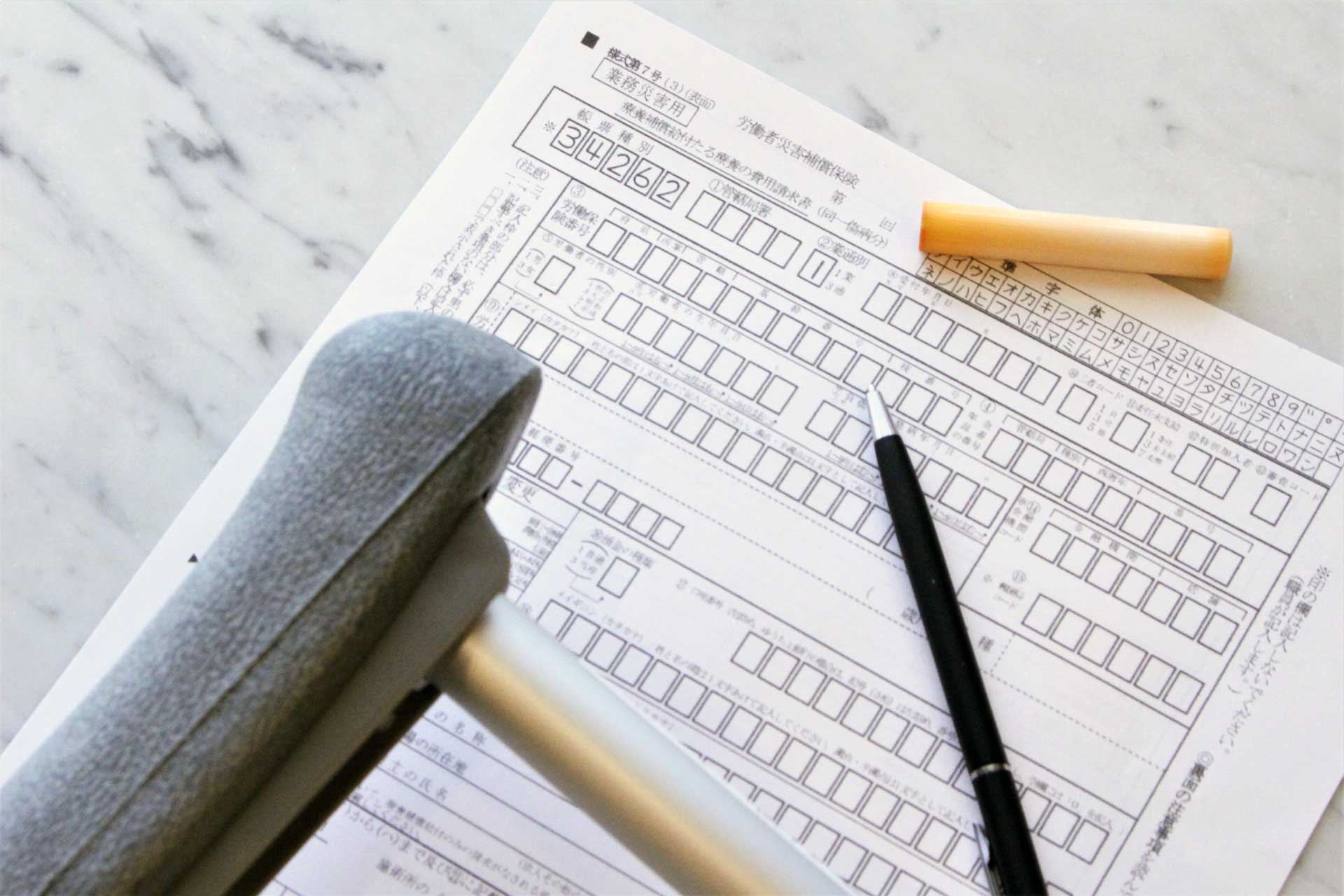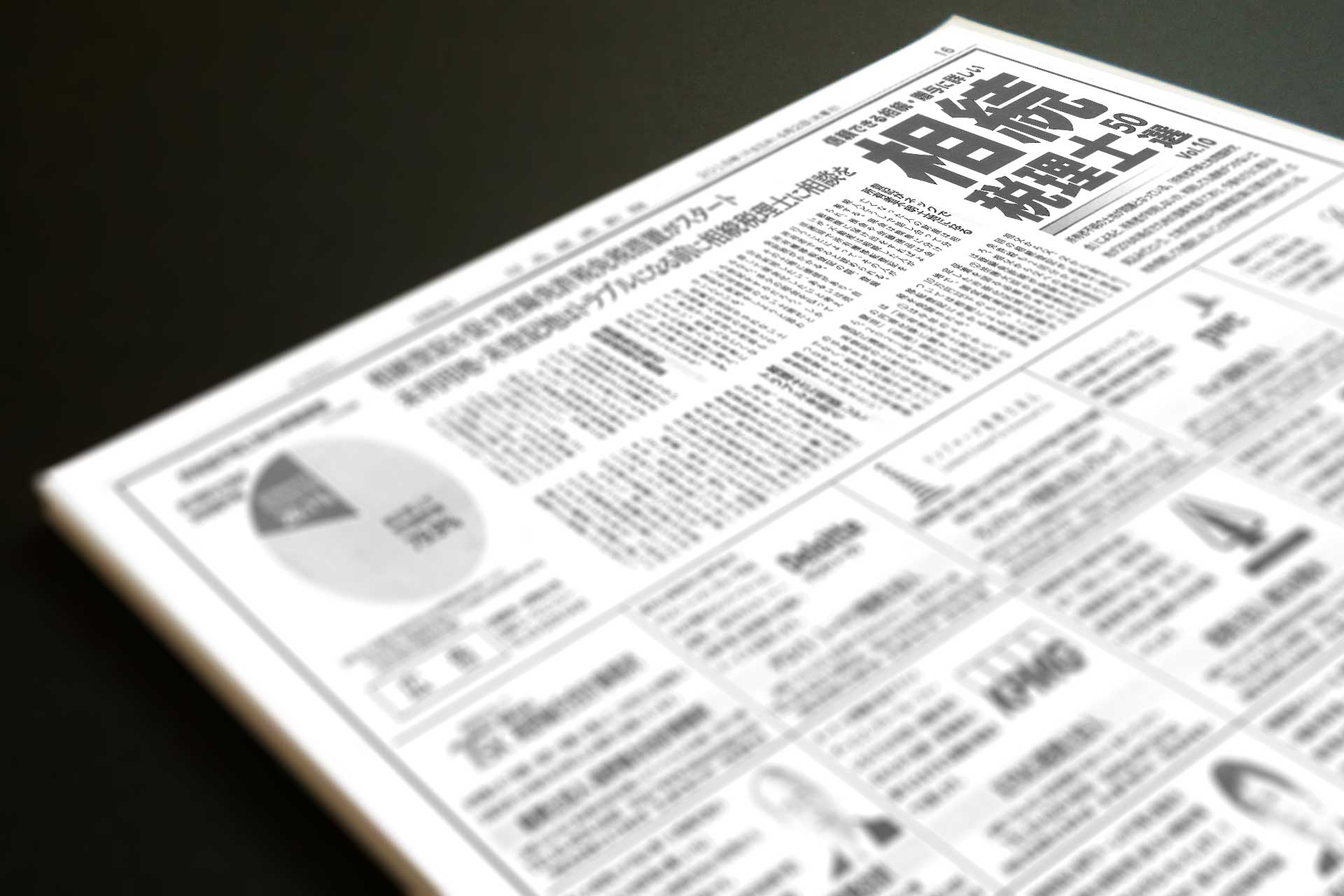遺言と相続に係る税務について提携弁護士と職員研修をお引き受けします。
研修内容概要
次のようなカリキュラムが一般的ですが、ご要望に応じ、初級、中級、上級と分けることもできます。このほか、オーダーメイドの研修もお引き受け致します。
研修内容及び講師派遣料金は、代表税理士田中までご相談ください。
カリキュラム(案)
入門編
- 遺言執行、遺産整理に必要な民法の知識と実務
- 相続・遺贈・贈与に係る税務の知識と実務
- 土地、非上場株式の評価と譲渡に係る税務の知識と実務
I.遺言執行、遺産整理に必要な民法の知識と実務
(1)研修の方針
被相続人、配偶者、子供二人の家庭をモデルに、被相続人の財産状態等に応じて幾つかのストーリーを設定し、そのストーリーの中で相続及び遺言について学ぶ。
研修の対象者は、相続及び遺言の実務経験の少ない方(初級者)
(2)研修時間
1時限90分✕8時限
(3)カリキュラム
≪一日目≫
1限目【相続の基礎】
テーマ:被相続人が亡くなったとき、家族は?被相続人の負債は相続人の債務?
研修の目的:相続の基礎、相続の対象となる財産と相続する人が誰かを理解する
内容
- 相続人の範囲、順位
- 相続人の確定(相続関係の調査方法、戸籍の読み方)
- 法定相続分
- 相続財産の範囲、権利義務の承継
- 単純承認、限定承認、相続放棄
- ドリル(復習)
トピック:婚外子の相続分(判例解説)
2限目【遺産分割】
テーマ:遺言書がない場合、遺産をどう分ける?
研修目的:遺産の範囲、遺産の評価、遺産の分割方法を理解する
内容
- 遺産分割の対象となる財産の範囲、評価
- 特別受益・寄与分
- 具体的な相続分の算定・分割方法
- 遺産分割調停・遺産分割審判
- ドリル(復習)
トピック:銀行預金と遺産分割(判例解説)
3限目【遺言書】
テーマ:相続人のために被相続人が生前にできることは?
研修目的:遺言書を作成する意義・実益とその限界を理解する
内容
- 遺言書を作成する意義
- 遺言書の種類
- 遺言の効力要件(無効が争われるケース)
- 遺贈と「相続させる」旨の遺言について
- ドリル(復習)
トピック:大きな勘違い、遺言と債務の承継
4限目【遺留分】
テーマ:被相続人の公平、相続人の不平等?
研修目的:遺留分を侵害すると相続が争族となることを理解する
内容
- 遺留分制度
- 具体的な遺留分額の算定方法
- 遺留分侵害に対する減殺請求の行使方法
- 遺留分減殺請求後の法律関係
- ドリル(復習)
トピック:事業承継円滑法における遺留分特例制度
≪二日目≫
5限目【相続関連制度】
テーマ:相続に関連して活用できる制度は?
研修目的:相続を円滑なものとするための補助的手段、または代替手段を理解する
内容
- 財産管理契約・任意後見契約
- 信託
- ドリル(復習)
トピック:遺言と信託のメリット・デメリット
6限目【実務模擬研修】
テーマ:遺言書の検認申請書を作成する
研修目的:検認申請を通じて、自筆証書遺言が抱える法的問題点を理解し、また戸籍謄本をもとに相続人を確定する手順を理解する
内容
- 検認の意義・効果・手続
- 設例をもとに検認申請書の作成・添削
7限目【実務模擬研修】
テーマ:遺言書を自分で書いてみる
研修目的:遺言書は書き方一つで遺言書そのものが無効となり、また書き方を変えることによって法的な効果も変わることを理解する
内容
- 3限目遺言書の復習
- 設例をもとに自筆証書遺言の作成・添削
8限目【事例研究】
テーマ:相続マニュアルの検証
研修目的:受講者の属する金融機関の相続マニュアルを検証し、各規定の実務的意義を理解する
内容
- 受講生が相続マニュアルの内容を説明
- マニュアルの各規程の実務的意義、また問題点について解説
作成者
〒530-0003
大阪市北区堂島1-1-5
梅田新道ビル10階
黎明国際法律事務所
弁護士 曉 琢也
06-6147-6238
II. 相続・遺贈・贈与に係る税務の知識と実務
基礎編
(1)研修の方針
- 相続税・贈与税に関する基礎知識を Q&A の形式で学ぶ
- 土地の評価方法につき事例を中心に基礎から応用例まで学ぶ
- 非上場株式の譲渡に係る税務を習得する。
- 研修の対象者は、相続及び遺言の実務経験の少ない方(初級者)
(2)研修時間
1時限90分×15時限
(3)カリキュラム
≪一日目≫
1限目【相続税の計算と課税財産の範囲】
テーマ:相続税の課税対象財産と計算の仕組みを理解する
【Q&A】
- 相続税の課税方式について。
- 課税価格の合計額が基礎控除以下なら相続税の申告はしなくてもよいか。
- 配偶者は基本的に税金がかからないシステムになっていると聞くが本当か。課税されない場合、相続税の申告書も提出しなくていいのか。
- 二次相続を考慮した遺産の分割方法のモデル。
- 「相続税の総額」という概念を理解する。相続税の総額を算出した後、実際に納付する相続税額は加算されて増えたり、控除されて減ったりするか。
- 相続税の課税対象とされる財産は、相続財産に限らないか。
- 相続税が課税される(民法上の)相続財産はどんなものがあるか。
- みなし相続財産とはどのようなものをいうのか。
- 相続開始前の過去に行われた贈与財産も相続税の課税対象とされることがあるのか。
- 死亡保険金に対する税金は相続税とは限らない。どのようなケースでどのような税金が課税されるのか
- Aが亡くなった。相続人は子Bだけ。Aの妹が死亡保険金を受け取った。保険料はAが負担していた。この場合、相続税の課税対象となるが、死亡保険金は法定相続人一人当たり500万円まで非課税となるので、妹が相続した保険に税金はかからないか。
- 死亡退職金の非課税規定の適用対象者について。
- 相続税の非課税財産について。
ドリル(復習)
2限目【自宅の小規模宅地特例を理解する】
テーマ:本来、相続税法は遺産の分け方によって相続税の総額が変わらないように配慮しているが、小規模宅地等の課税価格の特例はこの原則を大きく変更している。相続税対策コンサルにもっとも重要な小規模宅地等特例を理解する
【Q&A】
- 自宅の敷地や商売に使っている土地の相続税が安くなる特例(小規模宅地等の課税価格の特例)の立法趣旨。
- 自宅の小規模宅地等特例の要件。
- 被相続人と生計を一にする親族の居住用の敷地の適用要件。
- 老人ホーム特例の適用要件
- 被相続人が居住していた住宅は娘家族も住んでいる二世帯住宅。被相続人が住んでいた部分以外のもっぱら娘家族が住んでいる部分の敷地についても80%減額特例の適用はあるか。二世帯住宅は一階に被相続人が二階に娘家族が居住している。
ドリル(復習)
3限目【特定同族会社事業用宅地等小規模宅地等特例を理解する】
テーマ:商店街のコンサルに重要な商売用の土地(同族事業法人に賃貸している土地を含む)及び貸付事業用小規模宅地等特例を理解する
【Q&A】
- 小規模宅地等の特例は賃貸アパートや駐車場の敷地にも適用できる特例(貸付事業用宅地等の特例)の適用要件。
- 貸付事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けで相当の対価を得て継続的に行うもの(準事業)も含まれるか
- 青空駐車場も賃貸していることに変わりはないが、200㎡まで50%減額される特例の適用はない理由。
- 自宅や貸付用不動産以外にも特定の対象となる宅地等はあるか。
- 特定同族会社事業用宅地等とはどのような宅地等をいうのか
- 特定事業用宅地等とはどのような宅地等をいうのか。
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等であっても、小規模宅地等の特例の適用がない土地があるが、どのような点に気を付けなければならないか。
- 限度面積の計算はどのようにするのか。
- 小規模宅地等の特例を受けるための手続き。
ドリル(復習)
4限目【相続税の申告と納税】
テーマ:相続税の申告から納税までの仕組みを理解する
【Q&A】
- 相続税の申告期限と申告方法。
- 相続税の申告までのタイムスケジュール。
- 相続税の納税方法。
- 延納
- 延納の要件である「金銭で納付することが困難」とはどのように判定するのか。
- 物納とはどのような制度か
- 物納ができる財産にはどのようなものがあるか
- 物納にあてることができる財産の種類及び順位。
- 物納できない財産はどのようなものがあるか
- 物納劣後財産とはどのような財産をいうのか
- 物納劣後財産にはどのような物があるか
ドリル(復習)
≪二日目≫
5限目【贈与税の基本的な仕組みと計算方法】
テーマ:贈与税の基本的な仕組みと計算方法及び実務に必要な贈与税の限界税率と実効税率の使い方を習得する
【Q&A】
- なぜ贈与税は相続税の補完税といわれるのか
- 一般社団法人・財団法人など持分の定めのない法人に財産を贈与して相続税を回避しようとする方法の可否。
- 暦年贈与は相続税対策効果(実効税率)
- 暦年贈与の相続税対策効果(限界税率)
- 一般贈与財産と特例贈与財産の違いはなんですか。
- 一般贈与財産用の税率表と特例贈与財産用の税率表は異なるか。
- 贈与税額はどのように計算するのか。
- Aは、昨年一年間に叔父から100 万円を祖父から400万円の合計500万円の金銭贈与を受けた。贈与税の計算はどのようにしたらよいか。
- 贈与税の申告手続。
- 相続時精算課税制度の概要。
- 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算はどのようにするのか。
- 相続時精算課税制度を選択した贈与者A(特定贈与者)が亡くなった。Aの相続税の計算を行うとき相続時精算課税により受けた過去の贈与と支払っている贈与税はどのように影響するのか。
- 相続時精算課税制度のメリットとデメリット。
ドリル(復習)
◇6限目・贈与税の基本的な仕組みと計算方法
テーマ:贈与税の基本的な仕組みと計算方法及び実務に必要な贈与税の限界税率と実効税率の使い方を習得する
【Q&A】
- 戸籍上の婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるが、適用に当たり注意すべきこと。
- 贈与税の配偶者控除を使い、住んでいる自宅の敷地を妻に贈与したい。具体的にはどのように行動したらよいか。
- 贈与税の配偶者特別控除を受けるための申告にはどのような添付書類が必要か。
- 直系尊属から住宅資金等の贈与を非課税で受けることができる特例の概要。
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる人(受贈者)はどのような人か。
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる住宅資金等の範囲を教えてください。
- 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた受贈者が取得や増改築をする家屋はどのような家屋でなければならないのでしょうか。
- 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税制度は、土地の購入も対象になりますか。
- 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税特例は、暦年贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用できますか。
- 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが制度の概要を教えてください。
- 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、受贈者はどのような者である必要がありますか。
- 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、住宅取得資金の範囲を教えてください。
- 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、取得する家屋の範囲を教えてください。
- 20歳以上の子どもや孫が直系尊属から贈与を受けた資金で自己の居住用に供する住宅を取得する場合は、親や祖父母など直系尊属が60才未満でも相続時精算課税を選択のできる制度があるそうですが、その適用手続きについて教えてください。
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について説明してください。
ドリル(復習)
7限目【ケーススタディ1】
テーマ:既に習得した知識を基に顧客に対し「不動産を購入する時は法人が有利なのか個人が有利なのか」を多角的に説明できるようにする。
Q.不動産を購入する時に法人で買うべきか個人で買うべきでしょうか。有利不利を教えてください。
8限目【ケーススタディ2】
テーマ:自宅の小規模宅地等課税価格の特例は遺言ビジネスの要といっても過言ではありません。
自宅の小規模宅地等特例について数種類の事例を想定しコンサルのポイントを理解し現実に活用できるレベルまで引き上げます。
事例研究
≪三日目≫
9限目【ケーススタディ】
テーマ:自営業者が自宅と共に事業用不動産(店舗、事務所、工場等の敷地)について小規模宅地等課税価格の特例が使えるか否かで相続税は大幅に変わります。開業医の相続対策を事例に小規模宅地等特例を徹底的に理解し活用できるように研修します。
事例研究
10限目【評価の基本的な考え方】
- 土地評価の区分
- 評価単位
- 通達等における評価減の主な規定
- 路線価
11限目【判断の難しい評価の考え方】
- 広大地評価
- 利用価値が著しく低下している宅地の評価
12限目【自己株式を中心とした非上場株式に関する税務】
- 株式等の譲渡課税
- みなし配当
- 自己株式を譲渡した場合の課税関
- 自己株式と所得税法59条(みなし譲渡所得課税)
- 相続財産に係る非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
- 保証債務を履行した場合の所得計算の特例
≪四日目≫
13限目【非上場株式の譲渡価額(適正な時価の算定)】
- 個人や法人が所有する非上場株式を譲渡する時の適正な時価の考え方
- 金庫株の取得・処分は「資本等取引」か
14限目【非上場株式の譲渡価額(適正な時価の算定)】
- その他の利益の享受
発行法人が自己株式を時価よりも低額で取得した場合における他の株主への贈与課税 - まとめドリル
15限目【想定遺産額2億円までの顧客とそれ以上の顧客のコンサル技術について】
- 想定資産額2億円間の顧客は30分から1時間程度のヒヤリングで想定税額や小規模宅地の問題点を説明し、遺言の必要性、遊休不動産の処分、生命保険や遺言代用信託の活用の提案をできるようにする。
- 想定資産額が2億円を超える顧客については、十分なヒヤリングと専門家の活用により問題点の抽出や提案をできるようにする。
作成者
〒100‐0005
東京都千代田区丸の内1-6-1
丸の内センタービル17階
JTMI 税理士法人 日本税務総研
税理士 田中耕司
03-6269-9751
相談予約はこちらから