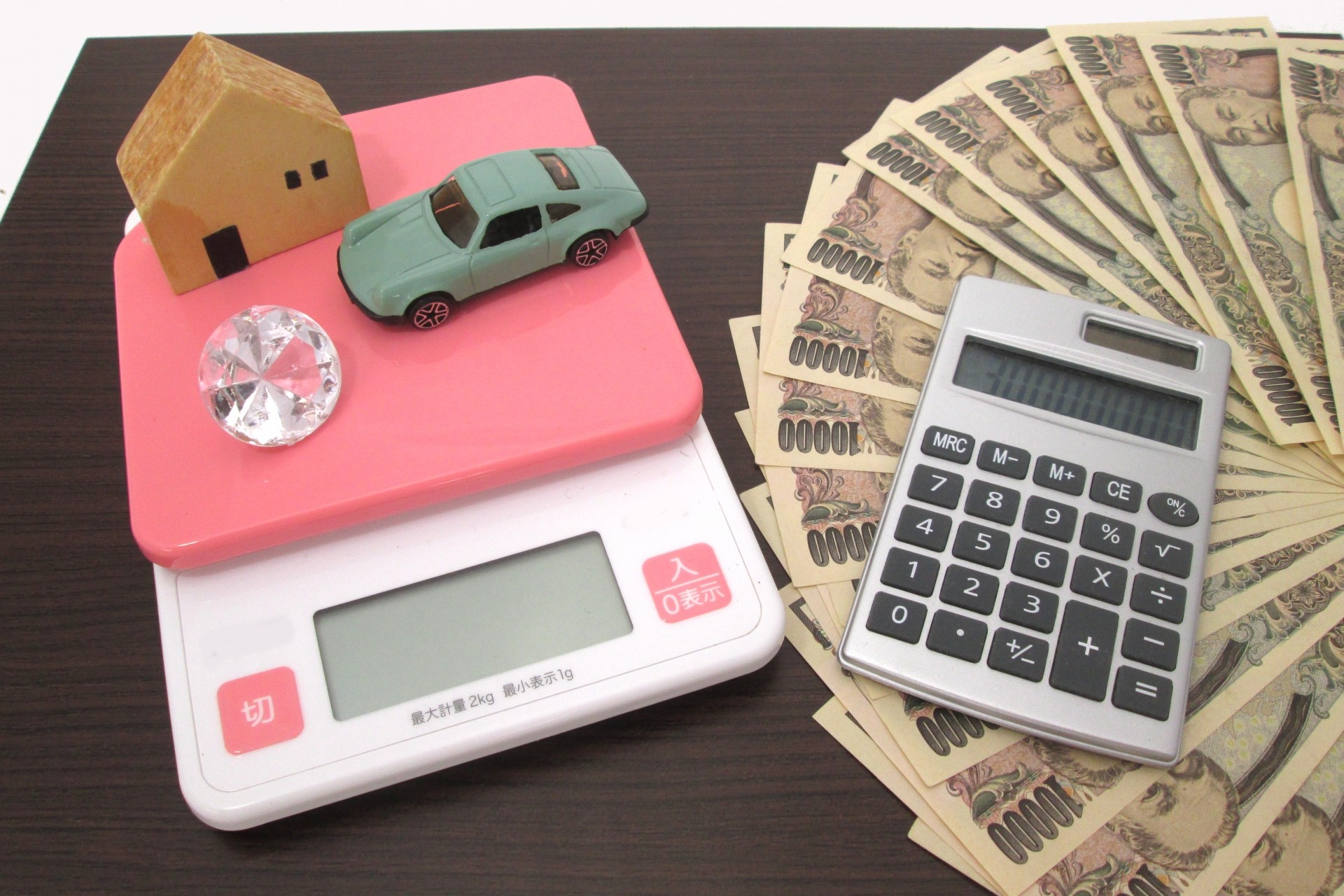法人に対し譲渡所得の基因となる資産の遺贈が行われた場合には、時価で譲渡されたものとみなされる(所法59①一)。個人間の遺贈ならば、受遺者には相続税を課税し、遺贈者が遺贈財産を取得した時期や取得価額を受贈者に引き継がせることにより、遺贈者が所有していた間に生じた資産の値上がり益を受贈者に引き継がせ、将来、受遺者が受遺財産を譲渡したときに譲渡所得課税を受けることとされている(所法60)。個人から法人に対する遺贈において、同様の取り扱いを行うと、本来、所得税が課税されるべき値上がり益(個人が所有していた間の値上がり益)が法人に引き継がれ、所得税が課税されず法人税が課税されるという不合理な結果を生じてしまう(1)。
(1)速報税理2008.8.1 小林栢弘「法人に対する特定遺贈とみなし譲渡所得課税の適用は?」
このため、法人に対する資産の無償譲渡(遺贈、死因贈与、贈与)については、個人から法人に支配権の移転があったときの「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税を行い、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法59条1項1号の規定である。この規定は、法人に対する遺贈においては、「時価」で譲渡したとみなすことに主眼がある。
法人に対する遺贈が時価で譲渡したものとみなされる結果、遺贈財産に含み益があれば、遺贈者は譲渡所得の申告が必要となる(所法59①一)。遺贈者の死亡により遺言の効果が生ずるのであるから、遺贈者の相続人は相続開始を知った日の翌日から四ヶ月以内に準確定申告を行い(所法124)、納税義務を負わなければならない(通法5)。法人に対する遺贈が特定遺贈ならば、特定遺贈の受遺者は遺贈者の準確定申告に関しては、申告義務も納税義務も負わない(2)が、包括遺贈ならば、包括受遺者は被相続人の債務を承継するから包括受遺者である法人も準確定申告の共同提出義務を負い、納税義務を承継する。相続人や受遺者が複数いる場合には、それぞれの者が承継する国税の額は、民法900条から902条までの規定(法定相続分・遺言による相続分の指定)による相続分により按分して計算した額によるものとされている(3)。その者の負担すべき国税の額が相続によって得た財産の額を超えるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)はその額を限度とし、他の相続人がその納付義務を負うものと規定されている(通法5②③)。
(2)第二次納税義務を負担することはある(国徴法39)。
(3)これに対し相続税の課税各区は、民法900条から903条(特別受益)による相続分により計算する。三年内加算の対象となる相続開始前の贈与は特別受益にあたるからである。
このように、遺贈者の準確定申告と納税義務は相続人及び包括受遺者が承継する。このため、土地や株式など含み益のある資産を法人に対し特定遺贈する場合には、相続人が納税資金に苦しまないようにあらかじめ考慮する必要が生ずる。
時価5,000万円の土地を法人に特定遺贈すると、取得費が収入金額の5%ならば、712万円ほどの所得税を負担することになる(5,000万円X(1-5%)x15.315%≒727万円)(4)。
(4)住民税の課税時期である翌年の1月1日には納税義務者である被相続人は存在しないので住民税(5%)は課税されない。
所得税の納税資金を相続人に相続させる方法も考えられるが、この場合には、相続により取得する資金に相続税が課税される。このようなことから、法人に特定遺贈する場合には、準確定申告における譲渡所得の税金相当額を受遺者である法人に負担させるよう負担付遺贈を行う等の配慮をすることも検討に値する方法である。
ただし、公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人に対し土地等の資産を遺贈するときに、あらかじめ譲渡所得税相当額の金額を負担する内容の負担付遺贈にすると、公益法人等に対する譲渡所得の非課税規定(措法40)が適用できなくなるので注意が必要である。租税特別措置法40条は、法人に対する贈与又は遺贈に関する所得税法59条1項1号の特別規定である、負担という実質的な対価を伴う資産の移転ならば、無償の資産の移転を前提とする59条1項1号の適用はなく、租税特別措置法40条の規定の適用の余地はなくなるのである。
所得税法59条の規定する「法人」には、営利法人だけでなく、人格なき社団・財団、持分の定めのない法人、国又は地方公共団体も含まれる。
人格なき社団や財団(以下、「人格なき社団等」という。)に対し遺贈が行われた場合には、人格なき社団等は個人とみなされ相続税が課税されるが、(遺贈資産が譲渡所得の基因となる資産であれば)同時に遺贈者に対し所得税法59条1項1号が適用され遺贈資産は時価で譲渡されたものとみなされ、遺贈者に譲渡所得課税が行われる。
人格なき社団等は、民法上は法人格を有しないが、所得税法上では、代表者又は管理人の定めのある人格のない社団等は法人とみなされるので(所法4)(5)、所得税法59条の規定する「法人」に含まれるのである。
(5)法人税法では、収益事業を行う場合に法人税の納税義務者となるとされている(法法4①)。
持分の定めのない法人や国又は地方公共団体は、法人格を有するから持分の定めのない法人に対する遺贈は「時価」で譲渡されたものとみなされる。
ただし、国又は地方公共団体に対し財産を遺贈(寄付)した場合にまで譲渡所得課税の対象とするのは適当ではないので、国又は地方公共団体に遺贈したときは租税特別措置法40条《国等に対し財産を譲渡した場合の譲渡所得等の非課税》により所得税法59条1項1号の規定する遺贈はなかったものとみなされ、譲渡所得の課税は行わないこととされている(措法40①)。
また、遺贈を受ける法人が公益認定委員会により認定された公益社団法人、公益財団法人や公益認定を受けることはできないものの、非営利型法人である特定一般法人(6)、その他公益を目的とする事業を行う法人(注)である場合には、民間の行う公益活動を促進する観点から、これらの法人に対する財産の遺贈についても、遺贈が公益の増進に著しく寄与すること、遺贈された財産(国外財産は除かれる。)が二年以内に公益目的事業の用に供されるなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を得たときは、国又は地方公共団体に対する遺贈と同様に、所得税法59条1項1号の規定については遺贈がなかったものとみなすこととされている(措法40①後段)。
(注)外国法人は除かれる。人格なき社団等は含まない。財団である医療法人及び持分の定めのない医療法人を含む。
(6)非営利型法人として、事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人であって(法法2①九の二イ)、その事業を運営するための組織が適正であるための所定の要件に該当しなければならない(法令3、措法40①)。非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人のうち、「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」として所定の要件を全て満たしている法人をいい(法法2九の二)、所定の要件を満たせば特に申請する必要もなく法人税法上の公益法人等として取り扱われ、国税庁が定める34種の収益事業以外から得た所得については法人税が非課税となるが、公益社団法人・財団法人とは異なり、非営利事業に係る金融資産の利子・配当にも源泉所得税が課され、収益事業等から生ずる所得とは通算されない(法令3)。
国税庁長官の承認を受けた財産の遺贈につき、一定の要件を満たさないこととなったときは、国税庁長官は承認を取り消すことができる。この場合に、遺贈された財産を公益事業の用に供する前に承認取消事由が生じたときは、遺贈をした個人に対し遺贈があったときの時価に相当する金額で譲渡があったとみなして譲渡所得課税が行われる。課税年分は、遺贈があった日の属する年分である(措法40②、措令25の17②)(7)。
(7)遺贈ではなく贈与があった場合にも同様の取り扱いとなるが、承認が取り消された贈与のみなし譲渡所得の課税年分は、贈与の非課税承認が取り消された日の属する年分となる。非課税承認取消の日までに贈与者がすでに死亡している場合は、贈与者が死亡した日の属する年分となる。
遺贈された財産を公益事業の用に供した後に、譲渡所得の非課税の承認取消事由が生じたときは、遺贈を行った個人に譲渡所得の課税を行うのは過酷であり、承認取消まで相当の期間が経過していることも考えられるので、遺贈を行った個人に対しみなし譲渡所得の課税を行うのではなく、公益を目的とする事業を行う法人を遺贈した個人とみなして、遺贈を受けた公益を目的とする事業を行う法人に対しみなし譲渡所得課税が行われる(措法40③)。
図表Ⅱ-33 法人に対する遺贈に係るみなし譲渡課税整理表
| 受遺者 | 遺贈者 | 申告方法等 |
|---|
| 普通法人 | みなし譲渡所得の課税
(所法59①一) | 被相続人に課税
(準確定申告) |
| 代表者又は管理人の定めのある人格なき社団又は財団 | みなし譲渡所得の課税
(所法59①一) | 被相続人に課税
(準確定申告) |
| 公益社団法人、公益財団法人や特定一般法人、その他公益を目的とする事業を行う法人(財団である医療法人及び持分の定めのない社団である医療法人を含む。外国法人は含まない。) | みなし譲渡所得の課税
(所法59①一) | 被相続人に課税
(準確定申告) |
| 国等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税 | 国税庁長官の承認
譲渡所得非課税 |
| 非課税承認取消 |
| 公益事業に供する前に承認取消 | 公益事業に供した後に承認取消 |
| (措法40、措令25の17、措規18の19) | 被相続人に課税
(準確定申告) | 公益目的事業を行う法人を個人とみなして譲渡所得課税 |
図表Ⅱ-34 非営利法人に対する課税の取扱い
| 公益社団法人、公益財団法人 | 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人 | その他の公益法人等(日本赤十字社等) | 認定特定非営利法人、仮認定特定非営利活動法人 | 特定非営利活動法人 | 非営利型の一般社団法人、一般財団法人(注1) | 一般社団法人、一般財団法人 |
|---|
| 課税対象 | 収益事業課税、ただし、公益目的事業に該当するものは、収益事業であっても非課税 | 収益事業課税 | 収益事業課税 | 収益事業課税 | 収益事業課税 | 収益事業課税 | 全所得課税 |
| みなし寄付金損金算入限度額(注2) | 次のいずれか多い金額
①所得金額の50%
②公益目的事業の実施に必要な金額 | 次のいずれか多い金額
①所得金額の50%
②年200万円 | 所得金額の20% | 次のいずれか多い金額(仮認定特定非営利活動法人は適用なし)
①所得金額の50%
②年200万円 | なし | なし | なし |
| 法人税率 | 23.9%
(所得年800万円まで15%(注3)) | 19%
(所得年800万円まで15%(注3)) | 19%
(所得年800万円まで15%(注3)) | 23.9%
(所得年800万円まで15%(注3)) | 23.9%
(所得年800万円まで15%(注3)) | 23.9%
(所得800万円まで15%(注3)) | 23.9%
(所得年800万円まで15%(注3)) |
金融資産収益
(注4) | 法人税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 収益事業から生じるもののみ課税 | 課税 |
所得税
(源泉徴収) | 非課税
(なし) | 非課税
(なし) | 非課税
(なし) | 課税
(あり) | 課税
(あり) | 課税
(あり) | 課税
(あり) |
| 寄付者に対する寄付優遇 | あり | あり | あり
(注5) | あり | なし | なし | なし |
(注1)非営利型の一般社団法人・一般財団法人:①非営利性が徹底された法人、②共益的活動を目的とする法人。
(注2)「みなし寄付金」とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、その支出した金額を寄付金の額とみなして、寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めるもの。
(注3)平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される。
(注4)法人税の課税対象となる利子・配当等の金融資産収益については、所得税額控除又は所得税額の還付の規定の適用あり。
(注5)特定公益増進法人等に該当する法人のみに適用される。
(出典)国税庁パンフレット 新たな公益法人関係税制の手引き
■非課税承認に係る財産を買い換えた場合の非課税制度の継続適用
寄付(贈与又は遺贈をいう。)を受けた公益法人が(譲渡所得の非課税規定≪措法40条1項後段≫の適用を受けた)寄附財産を、二年以上公益事業の用に供した後に譲渡し、譲渡による収入金額の全部に相当する金額を持って同様の資産を購入し、その資産を直接公益事業の用に供する場合には、譲渡の前日までに一定の書類を国税庁長官に提出する等の手続をとることにより、非課税制度の継続適用を受けることができる(措法40⑤、措規18の19⑫)。
二年以上直接公益目的事業の用に供しているかの期間判定
- 二年以上直接供しているかどうかの判定は、株式の場合、寄付を受けた日以後に寄付された株式から生じた果実を最初に公益目的事業の用に供した日をいう(措通40㉓)。
- 措置法40条5項に規定する「譲渡の日」とは、寄付を受けた財産の譲渡による引渡の日をいうものとして取り扱われる(措通40㉕)。
同種の資産の範囲
譲渡財産が株式である場合には、公社債及び投資信託の受益権は同種の資産に含まれるものとして取り扱われる(措規18の19⑪)。
ただし、割引債や無分配型(分配型であって利息が再投資されるものを含む。)の投資信託の受益権などのように、果実が生じない又は生ずる果実を公益目的事業の用に供することができない公社債及び投資信託の受益権は同種の資産に含まれない(措通40㉙)。