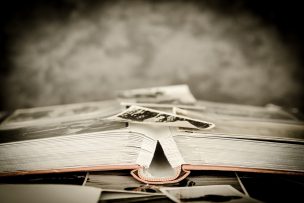小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人(まとめて相続人等という。)が事業用に使っていた家屋や構築物の敷地、被相続人等が自宅として使用していた建物の敷地(宅地や借地権)の課税価格を、納税者の選択により一定の面積まで減額できる規定である。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の制度趣旨は、生活や商売の拠点に使用している不動産の課税価格を一定の範囲において減額することにより、生活や事業の拠点が失われることを防止することである。
特例の対象となる宅地の種類は用途に応じ次の4種類となる。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等
特定居住用住宅地等についての計算の特例は、被相続人等が自宅に使用している土地の課税価格を330㎡まで80%減額する規定である。この特例の適用を受けるためには、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地(宅地及び宅地の上に存する権利)であることが必要である。
被相続人若しくは生計同一の親族が居住している建物は被相続人若しくは被相続人の親族が所有していることが必要であり、土地及び建物の使用は全て無償でなければならない。
本特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は相続開始前から被相続人と同居していた親族若しくは後に述べる一定の要件を満たす親族が、被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要である。配偶者が適用対象宅地等を取得した場合には特に要件は付されていないので、配偶者は生前から別居していても、相続開始後、他に転居しても、相続直後に売却しても本特例の適用を受けることができる。
被相続人と同居していた親族が取得した場合には、保有継続要件と居住継続要件が付されている。保有継続要件とは、適用対象宅地等を取得した同居の親族が法定申告期限まで所有していなければならないという要件であり、居住継続要件とは、被相続人と同居していた親族が適用対象物件にそのまま継続して居住しなければならないという要件である。同居の親族が本特例の適用を受けるためには両方の要件を満たす必要がある。
被相続人がなくなったときに配偶者も同居の親族(注1)もいなかった場合において、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有している日本国内に所在する家屋に居住したことがない親族(注2)が、相続又は遺贈により取得した場合には、取得した宅地等を法定申告期限まで保有していることを条件に本特例の適用が認められる。保有継続要件はあるが、居住継続要件はないのでわざわざ引っ越しをする必要はない。
(注1)ここでいう同居の親族とは相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における法定相続人をいうので、必ずしも一人住まいであることを意味しない。
(注2)制限納税義務者で日本国籍を有しない者は除かれる。
なお、本特例の適用を受けることができるのは、要件を満たす者が取得した土地で面積要件を満たす部分に限られる。
図表Ⅲ-11 相続権を失った者と相続税法の規定一覧表
| 利用状況と相続人 | 取得者と居住・所有継続要件 | 減額適用部分 |
|---|
| 被相続人の居住用 | 配偶者や同居の親族がいる場合 | 配偶者が取得 | ①要件を満たす者が取得した部分についてだけ特例適用対象となる
②遺産が一棟のビルであっても、居住の用に供されていた部分だけが特例適用対象となる |
| 同居の子供などが種痘し、居住を継続 |
| 配偶者や同居の法定相続人もいない場合 | 相続開始前3年間、日本国内にある自己又は自己の配偶者所有家屋に居住したことがない親族が取得(居住要件はない) |
| 生計を一にしていた親族の居住用 | 被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、相続開始前から申告期限まで居住を継続(被相続人の居住要件はない) |
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等についての計算の特例は、被相続人や生計同一の親族が事業に使っている建物若しくは構築物(注)の敷地(宅地又は宅地の上の権利)について一定の要件を具備すると400㎡まで課税価格を80%減額する規定である。
(注)次の建物又は構築物を除く。
・温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの
・暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは牧畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの。
特定事業用宅地等の「事業」には不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業や準事業を含まない。準事業とは事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものをいう。要は、土地の賃貸に関する事業は特定事業用宅地等の特例の対象とならないということである。いってみれば商売らしい商売に使っている建物などの敷地をイメージすれば間違いはない。
ところで、相続開始直前に事業を行っていたのが亡くなった本人であり、事業を継ぐ者がいない場合は、いかに被相続人の事業用の宅地であっても課税価格を減額する必要はない。そこで、被相続人が事業を営んでいた場合については、その土地を相続又は遺贈により取得する者が法定申告期限までにその事業を承継し、かつ、法定申告期限までその事業を営んでいることという事業承継要件が付されている。事業を承継し営むことが課税価格を減額する理由であるから、敷地も申告期限まで所有していることが必要であるという保有継続要件も付されている。気をつけなければいけないのは、「被相続人が営んでいた事業を承継しなければならない」ことである。事業用の宅地を相続した者が、父親の商売は面白くないからといって全く別の事業に転業した場合も本特例の適用を受けることはできない。ただ、被相続人の事業の一部を他の事業(不動産貸付業等の事業以外の事業に限る。)に転業している場合は、全体としてみれば承継している事業もあるので、事業承継要件は満たすこととなる。また、敷地の一部を譲渡したり貸し付けた場合も、残った敷地で事業が継続できるならば、継続している部分の敷地については本特例の適用が認められる。事業を承継し宅地等を相続した者が申告期限前に亡くなった場合は、その者の相続人が事業を承継し、かつ、所有を継続すれば本特例の適用が可能である。
なお、事業を営んでいるかどうかは、事業主として当該事業を行っているかどうかにより判定するのであるが、敷地を取得した事業を引き継いだ親族が就学中であることその他当面事業主となれないことについてやむを得ない事情があるため、事業を引き継いだ親族の親族が事業主となっている場合には、敷地を取得した親族が引き継いだ事業を営んでいるものとして取り扱うこととされている。また、会社等に勤務するなど他に職を有し、又は被相続人が営んでいた事業の他に主たる事業を有している場合であっても、被相続人が営んでいた事業の事業主となっている限り、これにあたるとされている。
事業を営んでいた父親が引退し、生計同一の子供が事業を継いだ後に父親が亡くなった場合や、父が所有している建物を生計同一の息子が無償で借りて息子が営む事業の用に使っていた場合など、被相続人と生計を一にする親族が被相続人の所有する土地の上の建物や構築物で相続開始前から事業を営んでいる場合にも、敷地の課税価格を減額する必要性はある。この場合も、事業を営んでいるものが敷地を相続し法定申告期限まで事業を継続し、敷地を保有しなくてはならないという事業継続要件と保有継続要件が付されている。営む事業はもともと相続人自身の事業なので、上述の被相続人の事業を承継した場合と異なり、事業内容を変えても事業そのものを継続するならば本特例の適用要件を満たすことになる。
数人共同で相続した場合、要件を満たすものが相続又は遺贈により取得した部分だけが減額対象となる。
なお、相続財産である被相続人所有の土地と建物の所有者が異なるときは土地の賃借及び建物の賃借について全て無償又は相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合に限り本特例の適用対象となる。被相続人が相当の対価にあたる地代を受理していたときは貸付事業に該当するので本特例の適用の余地はない。
また、生計同一の親族が所有している建物を被相続人が家賃(相当対価)を支払い借りているときは(土地は無償)、建物の賃貸借が「生計同一の親族の『貸付事業』にあたる」ので貸付事業用宅地等の特例の適用対象となり、本特例の適用の余地はない。
生計別の親族が所有している建物を被相続人が家賃(相当の対価)を支払い借りているときは(土地は無償)、小規模宅地等の特例の適用の余地はない。被相続人所有の敷地は、単なる「親族が賃貸している建物の敷地」にすぎないからである。
図表Ⅲ-12 特定事業用宅地等の適用要件概要
| 相続時の利用状況 | 適用要件 | 適用対象部分 |
|---|
| 被相続人の事業用 | その宅地・借地権の取得者が地上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで事業を継続していること | 数人共同で事業用宅地等を相続した場合、要件を満たす者が取得した部分だけが減額対象となる。 |
| 被相続人と生計同一の親族の事業用 | 相続開始直前から相続税の申告期限までその宅地等を保有していること |
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等についての計算の特例は、被相続人と被相続人の一族等が発行済株式総数(自己株及び議決権のない株式等を除く。)の50%を超える株式を保有する同族会社(営む事業が不動産賃貸業以外のもの)が、被相続人の所有する宅地・借地権の上の建物で事業を営み、その他一定の要件を満たす場合に最高400㎡まで敷地の課税価格を80%減額できるというものである。
特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が所有している宅地等を法人が直接相当の対価を支払い賃借し建物を所有しているか、被相続人等が地上建物を所有し法人に相当の対価で貸し付けていることが前提となる。租税特別措置法69条の4の条文構成は、1項で適用宅地を「被相続人若しくは生計同一の親族の事業の用に供されていた宅地等」とし、事業を①不動産貸付業又は②不動産貸付業以外の事業の2種類に分類している。また、同条3項3号は、「特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等」と規定しているので、単に特定同族会社の事業用の宅地であるにとどまらず、被相続人等により特定同族会社に不動産の貸付が行われている宅地等をいう。
建物所有者の区分と土地建物の貸付の態様を整理すると次のとおりである。なお、いずれの場合も法人が営む事業が不動産貸付業である場合は、貸付事業用宅地等にあたり、本特例の適用対象には該当しない。
- 建物所有者が同族法人である場合
被相続人が土地を法人に貸し付けている場合は、地代(相当の対価)を収受していることが必要である。 - 建物所有者が生計同一の親族である場合
被相続人が生計同一の親族から地代(相当の対価)を収受しているときは、貸付事業用宅地等にあたり、本特例の適用対象には該当しないから土地の賃借は無償でなければならない。また、生計同一の親族は建物を有償(相当の対価)で法人に貸し付けていなければならない(無償では事業に該当しない)。 - 地上建物を被相続人が所有しているときは建物は有償(相当の対価)で貸し付けられていなければならない(無償では事業に該当しない。)。
法人についての要件としては、相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族その他当該被相続人と特別の関係のある者の有する株式・出資(自己株及び議決権に制限のあるものを除く。)の50%を超える法人(申告期限において清算中の法人を除く。)であることが必要である。なお、上記の「特別の関係がある者」とは、次のとおりである。
- 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 被相続人の使用人
- 被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
- 次に掲げる法人
- 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
- 被相続人及びこれと5-1の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
- 被相続人及びこれと5-1又は5-2の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
この特例の適用を受けるためには、次の全ての要件を満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により宅地等を取得することが必要である(要件を満たす者が取得した部分だけ特例適用対象となる。)。
- 法人役員要件
相続税の申告期限においてその法人の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事など法人税法2条15号に規定する役員。ただし精算法人を除く。)であること - 保有継続要件
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
図表Ⅲ-13 特定同族会社事業用宅地等の適用要件概要
| 相続時の土地建物利用状況 | 適用要件 | 適用対象部分 |
|---|
| 被相続人の有する宅地等の上に特定同族会社の所有する建物等があり土地が賃貸されている場合 | 法人要件
・相続開始直前において被相続人及び被相続人の親族等で発行済株式総数の50%超を所有
・申告期限まで事業を継続
取得者要件
・申告期限において法人の役員であること
・申告期限までその宅地等を保有していること | 要件を満たす者が取得した部分についてだけ特例適用対象となる。 |
| 被相続人の有する宅地等の上に被相続人の所有する建物等があり建物が賃貸されている場合 |
| 被相続人の有する宅地等の上に生計を一とする親族の所有する建物等があり建物が賃貸されている場合(土地の賃借は無償) |
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等についての計算の特例は、被相続人若しくは生計同一の親族が行っている不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に供されていた宅地等を取得した者(被相続人の親族)が貸付事業承継要件や保有継続要件などの要件を備えたものである場合は200㎡まで課税価格を50%減額するものである。準事業とは事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいう。
相続又は遺贈により被相続人が貸付事業を行っていた宅地等を取得した親族は、相続開始時から申告期限までの間に貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、かつ、その貸付事業の用に供していることが必要である。
被相続人と生計同一の親族が相続開始前から自己の貸付事業を行っている場合は、相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限までその宅地等を自己の貸付事業の用に供していることが必要である。
図表Ⅲ-14 貸付事業用宅地等の適用要件概要
| 相続時の土地建物利用状況 | 適用要件 | 適用対象部分 |
|---|
| 被相続人の貸付事業用 | その宅地等の取得者が、申告期限まで保有し、その宅地等の上で営まれていた被相続人の貸付事業を承継し、その事業を継続していること | 要件を満たす者が取得した部分についてだけ特例適用対象となる。 |
| 被相続人と生計同一の親族の事業用 | その貸付事業を営んでいた親族が取得し、申告期限まで保有し、貸付事業を継続していること |
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)に、この特例の適用を受けようとする旨の記載及び計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用される。
具体的には、相続税の申告書第11表の付表1「小規模宅地等に係る課税価格の計算明細書」の提出を要するほか、適用する特例の規定に応じ、申告書等に図表Ⅲ-15に示したそれぞれの書類を添付する必要がある。
図表Ⅲ-15 添付書類一覧表
| 小規模宅地等の区分 | 取得者・根拠規定等 | 価格減割合 | 添付書類 |
| 戸籍謄本 | 遺言書の写し等 | 住民票の写し | 戸籍の附表の写し | その他 |
| 居住用宅地等 | 特定居住用宅地等 | 配偶者(措法69の4③二) | 80% | ○ | ○ | | | |
| 同居親族(措法69の4③ニイ) | ○ | ○ | ○ | | |
| 持家無し親族(措法69の4③ニロ) | ○ | ○ | ○ | ○ | 注1 |
| 生計を一とする親族(措法69の4③ニハ) | ○ | ○ | ○ | | |
| 事業用宅地等 | 特定事業用宅地等 | 措法69の4③一 | ○ | ○ | | | |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 措法69の4③三 | ○ | ○ | | | 注2 |
| 貸付事業用宅地等 | 措法69の4③四 | 50% | ○ | ○ | | | |
(注1)相続開始3年以内(3年前から相続開始直前までの間)に、その親族が居住していた家屋がその者又はその者の配偶者が所有するものではないことが分かる登記事項証明書などの資料
(注2)その法人が相続開始の直前における次の事項を証明した者及びその法人の定款の写し
①その法人の発行済株式総数(出資の総額)
②被相続人等の有する株式総数(出資金額の合計額)
戸籍謄本は、相続税の申告書を提出するときには必ず必要な添付書類であり、相続開始日から10日を経過した日以後に作成された謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするものであることが必要である(相規16③)。遺言書等の写しとは、遺言書又は遺産分割協議書・印鑑証明書(全ての共同相続人が自署及び実印で押印しているもの)をいう。
住民票の写し及び戸籍の附表が必要な者は、小規模宅地等を取得した親族である。なお、住民票の写し及び戸籍の附表は相続開始日以後に作成されたものに限る。
なお、外国人及び在外邦人の印鑑証明書等については図表Ⅲ-16参照。
図表Ⅲ-16 外国人及び在外邦人の印鑑証明等
| 外国人 | 本国の官公署又は在日公館の外国官憲の発行した署名証明書 |
| 大韓民国等のように印鑑証明制度のある国に居住している場合は、外国の印鑑証明書 |
| 日本に居住し、かつ、印鑑を使用している場合には、居住地の市町村長の発行した印鑑証明書 |
| 在外邦人 | 中華人民共和国のように居住地国の日本公館(領事館等)で印鑑証明の発行を行っている場合には、居住地国の日本公館が発行した印鑑証明書 |
| 居住地国の日本公館が印鑑証明書の発行を行っていない場合には、居住地国に日本公館が発行した署名及び拇印証明書(居住地国の日本公館が遠方にあるなどの場合は、外国の公証人が作成した遺産分割協議書の署名についての証明でも可) |
| 日本に一時帰国している間に、遺産分割協議書が成立したような場合には、日本の公証人による遺産分割協議書の署名についての証明 |
小規模宅地等の特例を適用した土地を申告期限後において選択替えすることは可能か
小規模宅地等の特例の適用対象宅地が複数ある場合には、どの宅地に特例を適用するかは納税者自身の選択に委ねられている。この場合一度選択して申告した特例適用宅地等について、申告期限後に選択替えをすることはできない。適法に手続きされた申告内容については、更正の請求(通法23)の理由とはなりえないからである。適用対象地の選択は慎重にする必要がある。
図表Ⅲ-17 小規模宅地の適用対象となる限度面積及び小規模宅地等の価格に乗じる割合
| 相続開始の直前の状況(用途区分) | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|
| 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 不動産貸付業等以外の事業用の宅地等 | 被相続人の事業用の宅地等 | ①特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業用の宅地等 | ②特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
| 不動産貸付業等の事業用の宅地等 | ③特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 |
| ④貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の居住用の宅地等 | ⑤特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地等 | ⑥特定居住宅地等に該当する宅地等 |
各特例の併用関係
- ①「特定同族会社事業用宅地等及び特定事業用宅地等」と②特定居住用宅地等は完全併用できることとされた(平成27年1月1日以降相続開始分)。
- 貸付事業用宅地等を選択する場合には、貸付事業用宅地等(上限200㎡)に換算して限度面積を判定する。
図表Ⅲ-18 小規模宅地等計算特例の併用計算図

図表Ⅲ-19 小規模宅地フローチャート(居住用)

図表Ⅲ-20 小規模宅地フローチャート(貸付事業用以外の事業用の宅地等)

図表Ⅲ-21 小規模宅地フローチャート(貸付事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等)