もちろんお引き受けします。
- 相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。
- 過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。
- 料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。
相談予約はこちらから
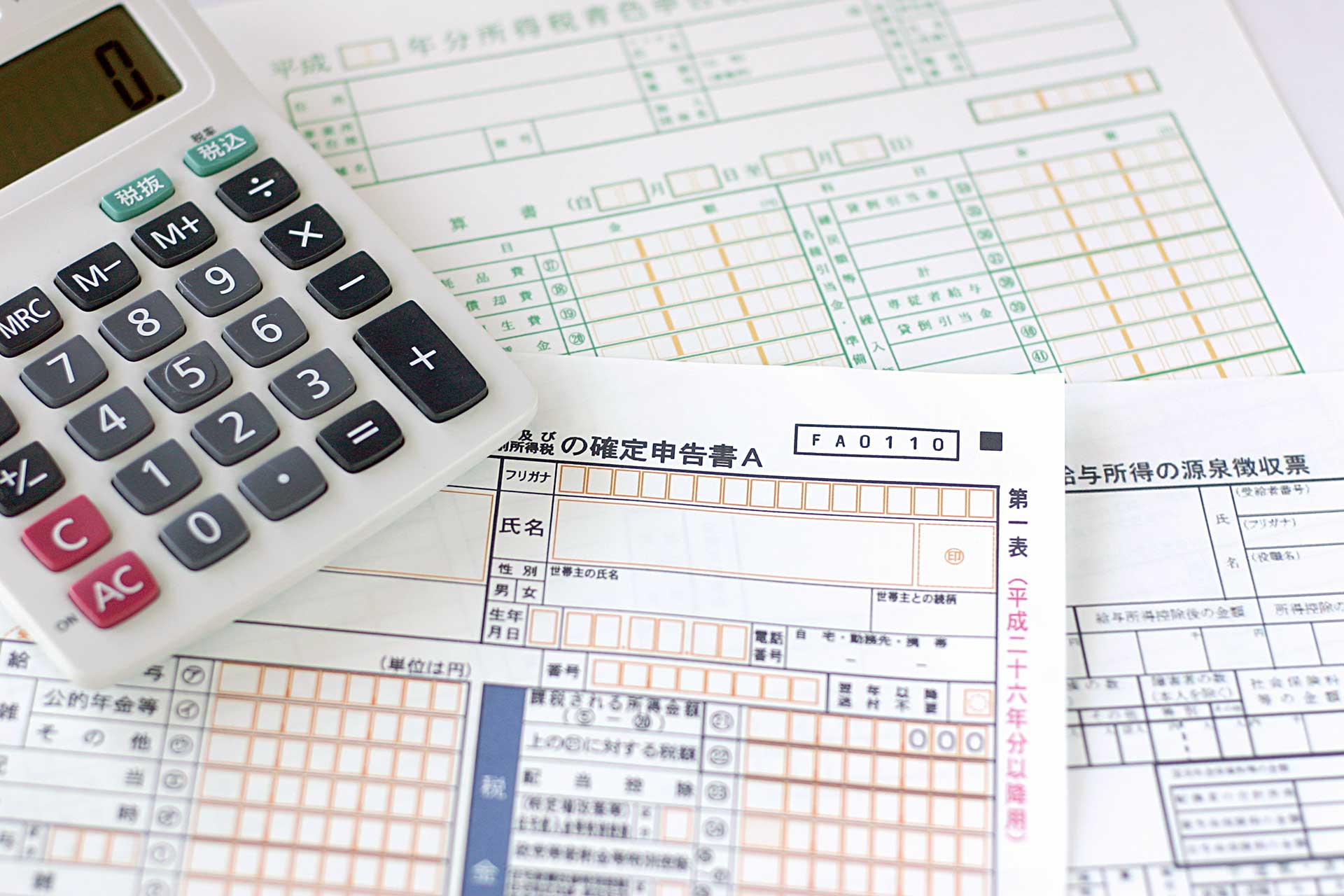
もちろんお引き受けします。
相談予約はこちらから

資料をPDFで送受信できる方(PDFを印刷できる環境にある方)が理想ですが、資料を郵送してメールで打合せ、というのは、いまでも基本的に行われている打ち合わせ方法です。遺産の額が1億円前後の方でしたら、ほとんどの打ち合わせや資料収集がこの方法で可能です。遺産規模が多くなればなるほどお目にかかって打ち合わせを行う必要が増大します。
税理士法人日本税務総研は平日朝8:30~晩7:30まで事務所は開いています。
メールでのご連絡は、当然のことですが時間の制約はありません。
海外の相続人の方とはメールまたは、時差に配慮して電話で連絡を差し上げています。
60歳くらいまで会社にお勤めだった方で、遺産の内容が不動産一カ所、金融資産は預貯金、上場株式、ご親戚に同族会社の経営者がいらっしゃらない方なら、遺産分割協議さえスムーズに完了すれば、初回と最終面談の2回だけで申告書を完成させることは可能です。
相談予約はこちらから

遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。
遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。
税理士法人日本税務総研のベテラン税理士は、あらかじめ同様のチェックを行い調査に備えたうえで、納税方法のアドバイスを差し上げます。
物納は現行法では5年の瑕疵担保責任を負います。相続税評価額以上で売れる(売ってもいい)不動産があれば、物納よりも売却の方が後々の負担は少ないのが現行実務です。
逆に、相続税評価額で売れない物件は、国に物納として取ってもらえば好都合です。
税理士法人日本税務総研には、物納制度に習熟した税理士がいます。物納を行う場合、相続税の申告と遺産分割を申告期限2ヶ月前に完了しておくことが必要です。(物納準備に1か月以上かかります。)ぜひ早めにご相談くださるようお願いします。
相談予約はこちらから

親子、親族間で無利息の金銭消費賃借を契約する場合があります。
例えば、子供が住居を購入するにあたり、親がその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか賃借なのかで課税額が変わります。
金額にも依りますが、親からの贈与として贈与税の課税を避けたいのであれば、きちんと弁済していることが一番です。これを証明するために、手渡しではなく銀行振込みなど、後日明確にできる方法で弁済する必要があります。
契約書の有無、利息の支払いも必要ですが、実際に返済の事実があれば贈与税を課税されることはありません。利息も少額であれば課税の対象にはなりません。
ただし、返済中に親が死亡した場合は貸付金として相続財産となります。
相談予約はこちらから
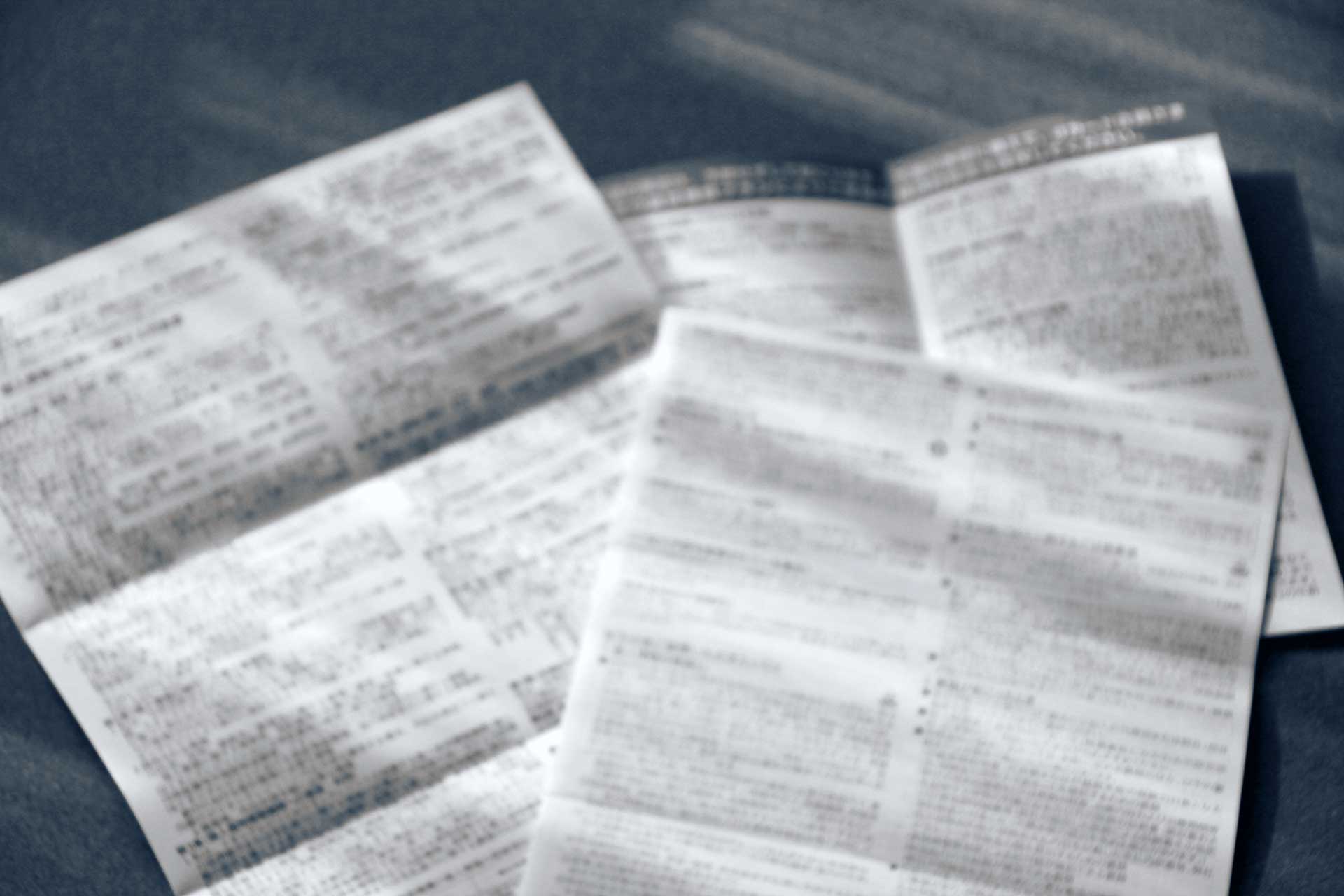
死亡保険契約を締結している方が亡くなったときは、保険金受取りの手続きを行なうと、死亡保険金が支給されます。
故人が加入していた生命保険を確認し、保険金の受取人となっている者が口頭、もしくは書面で保険会社に死亡の事実を知らせると、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
主な必要書類は次のとおりです。詳細は保険会社にお尋ねください。
これらの書類をそろえて生命保険会社に返送し、受理されると生命保険会社の定めた支払期限内に保険金が支払われます。
なお、保険金の請求は被保険者の死亡から3年以内にしなければなりません。
これを過ぎると、保険金を受け取る権利はなくなります。
法定相続人が受け取った死亡保険金(亡くなられた方が負担していた保険料に対応する保険金に限ります。)は、500万円×法定相続人数まで非課税です。
よくある誤り
法定相続人ではない孫が受け取った死亡保険金について、非課税規定は適用できないのに適用して計算してしまった。
相談予約はこちらから

良質な遺産相続税申告サービスを支える人材の多様性
税理士法人日本税務総研は、国税OBの税理士が中心となっていますが、それだけではありません。
プログラミングに精通した税理士、外資系金融機関でコンサルティングを担当していた税理士、国税不服審判所で審判官として活躍していた税理士、弁護士や公認会計士の資格を有する税理士など多彩な人材を有し、新たな事象が生じたときには、仲間と協力しつつ、総合力で皆様のお役に立つよう努めています。
税理士法人日本税務総研は、平成17年の創業以来、累計3,000件を超える申告書を作成し、現在は年間300件を超える相続案件を取り扱っています。
税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、原則として、すべての案件について、熱意を持って、税務署の調査官がチェックするポイントをあらかじめ押さえ、過不足のない遺産の把握と適正な評価、最も有利な特例の選択を行います。過去の入出金の分析から問題点を抽出するなど元調査官ならではの良質な申告サービスを提供しています。
税理士法人日本税務総研は、ベテランの税理士をそろえることで、効率の良い作業を実現し、報酬の実質的な低価格化を実現しているのです。
「同じ料金ならベテランの税理士に担当して欲しい」という皆様のご要望を実現し、多くのお客様から相続税申告のご依頼を頂いております。
財産評価は、国税庁が定める財産評価基本通達の規定を適用して行います。相続税法は、課税価格を「時価」と規定するだけで具体的な評価方法については詳細な規定を置いていません。
国税庁は、相続税の課税対象としての財産評価を上述の通達で行っています。
経験の浅い専門家は、「通達を駆使して」評価を下げようとする傾向がありますが、評価通達は、本来、保守主義の原則に立ち、適正な時価を算定しようとするものです。
「都合の良い通達の組み合わせ」で無理やり評価を下げても、「著しく時価と乖離した結果を招く」ならば税務調査で否認され、修正を余儀なくされてしまいます。
財産評価は、適正な評価が基本です。
不動産は、評価対象を現地踏査して確認することが基本です。セットバックの必要性や傾斜地の有無、都市計画の規制、高圧電線敷設のための地役権の設定などの調査は基本中の基本です。
税理士法人日本税務総研の税理士は、全ての土地について適正な評価を行うよう努めています。
他の税理士事務所が作成した評価誤りを抽出し、更正の請求により2億円の還付を受けた実績があります。
税務署、国税局に提出された申告書のおおよそ3割は、実地調査対象として選定され、調査を受けた申告書のうち約8割が修正申告書の提出を指導されています。
なぜ、調査を受けた10件のうち8件までもが誤りを指摘されるのでしょうか。税理士法人日本税務総研は、相続税の申告書を作成する税理士にも責任の一端があると考えています。
相続税の申告書は、被相続人に関する情報を十分に収集し、預貯金や株式の異動を調査して作成するのが基本です。
ご協力が得られれば、被相続人および家族名義の預貯金、顧客勘定元帳の入出金や入出庫の分析、過去の不明出金の有無などを分析検討して(税務調査で発見される)申告漏れ財産の可能性を排除していきます。
相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、2月24日に死亡した場合にはその年の12月24日が申告期限です。
この期限が土、日、祝日などに当たるときは、翌日が期限です。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますから、期限厳守は当然です。
申告期限を待たずに、早めに、例えば相続開始後半年以内に作ってほしいとおっしゃる方も少なくありません。
申告書の作成に必要な資料さえいただければ、できるだけ早めに申告書をお作りしています。
税理士法人日本税務総研は、資産税を専門とする国税OBが多数在籍しているので、大手の法律事務所などから相続税・贈与税のご質問を受ける機会も多く、遺言にかかる税務、法人に対する寄付、信託税制など多方面のご質問にお答えしています。
金融機関のFPの方から毎月20~30件のご質問をお受けしています。
大手不動産会社からは、不動産の譲渡や印紙税のご質問など、毎月十数回を超えるご質問をお受けしています。
税務弘報という雑誌の付録として、平成25年に「ネバー・エンディング・ノート」を上梓し、平成29年には読者のご依頼により改訂版「ネバー・エンディング・ノート2」を上梓しました。
また、毎年1月に発行される号(2月号)に確定申告の特例要件と必要書類を解説した「確定申告3要項」という記事を平成28年から毎年寄稿しています。
信託協会や金融機関、住宅メーカーからご依頼を受け、セミナー講師やパネルディスカッションのメンバーを派遣しています。
出版書籍は、次のとおりです。
この他、信託法制の展望(日本評論社5,800円+税)に代表税理士田中耕司が法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務を寄稿しています。
相談予約はこちらから

ゴーイング・コンサーン(going concern)
企業を繁栄・継続させることを最大の目標として、経営者は事業計画を立て、経営を導いています。そんな企業に対する大きなハードルが「相続と相続税」です。
事業承継後の会社の支配権の安定と相続税の合理的な節税を考えるのが事業承継計画です。
1.事前協議
2.事業承継計画会議
3.株主構成
事業承継計画は、会社を育てる計画の一環です。「株価を引き下げる」などという形式的なアドバイスは基本的に行いません。事業承継計画は、単なる相続税対策ではなく、事業をさらに成功させるための計画でなければならないと税理士法人日本税務総研は考えています。
相当の規模と社会的な存在を誇る法人については、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の検討を行います。税理士法人日本税務総研にご相談いただければ、事業承継税制の専門税理士が対応いたします。
税理士法人日本税務総研がご案内する事業承継計画の多くは、内容を十分に理解いただいた役員に事業計画の一環で実施していただきます。税理士法人日本税務総研は、事業承継によって生ずる税務問題に適切な対応を行うよう努めます。
金融機関からの提案について、メリットとデメリットをご説明します。
「日本税務総研のお話は、銀行や証券会社の提案とちょっと違いますね」というお言葉をよくいただきます。税理士法人日本税務総研は、税理士でなければできない事業承継のヒント(会社の実態や将来像を十分に理解したうえでなければできないご提案)をご提供するよう努めています。
法人税の申告書3期分と代表者の所得税の申告書3年分の写しを拝見した後、費用のお見積りを致します。
相談予約はこちらから

交通事故により受け取る損害賠償金の課税関係については次のように取り扱われます。
交通事故の被害者が死亡したことにより、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。
被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合は、損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
被害者が死亡したことについて支払われる損害賠償金は、所得税法上の非課税規定に該当しますので、所得税はかかりません。
相談予約はこちらから

など、不安に感じられたときは是非ご相談ください。
相続税専門の税理士法人日本税務総研は、大規模法人の法人税や消費税も専門です。ベテランの税理士が 相続税対策や現に起こっている相続だけでなく、次世代を視野にいれた分割と税務についてアドバイスを差し上げます。
評価対象地一か所当たり10万円(税抜)
*原則として日当、旅費を含みます。
*遠隔地(交通機関での移動距離150キロ超をいいます。)の旅費は別途ご相談させていただきます。
| 報酬額 | 130万円~(税抜) |
※ 会社が所有する不動産、有価証券等の資産評価を含みます。法人税の申告書・決算書・科目内訳書を過去3期分及び保有有価証券明細、不動産明細をご用意ください。推定稼働時間から見積額をご提示します。
相談予約はこちらから

相続税の計算方式は大きく分けて二通りあります。遺産課税方式と遺産取得課税方式です。
現行の相続税法は、相続または遺贈により財産を取得した人(原則として個人)に対し課税する遺産取得者課税方式を採用しています。
贈与税についても、財産を取得した受贈者を納税義務者としています。
純粋な遺産取得者課税方式は、相続または遺贈により実際に取得した額に応じ、各相続人が個別に申告します。この方式では、遺産を少人数で取得すると多人数で相続するよりも負担が重くなります。
そこで、兄弟三人のうち一人が全遺産を相続しても、三人で均等に相続したとするような仮想分割が横行する可能性があります。
このため、現行の相続税法は、相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の総額を算出する遺産取得者課税方式(法定相続分課税) を採用しています。
英米で採用されている遺産課税方式は、遺産そのものに相続税を課税します。
遺産管理人や遺言執行者などは、あらかじめ相続財産から相続税を納税し、その後、相続人や受遺者に遺産を分割します。贈与税についても贈与者を納税義務者としています。
米国歳入庁(IRS)は、ホームページで相続税(Estate Tax)を次のように定義しています。
The Estate Tax is a tax on your right to transfer property at your death.
Internal Revenue Service
相談予約はこちらから