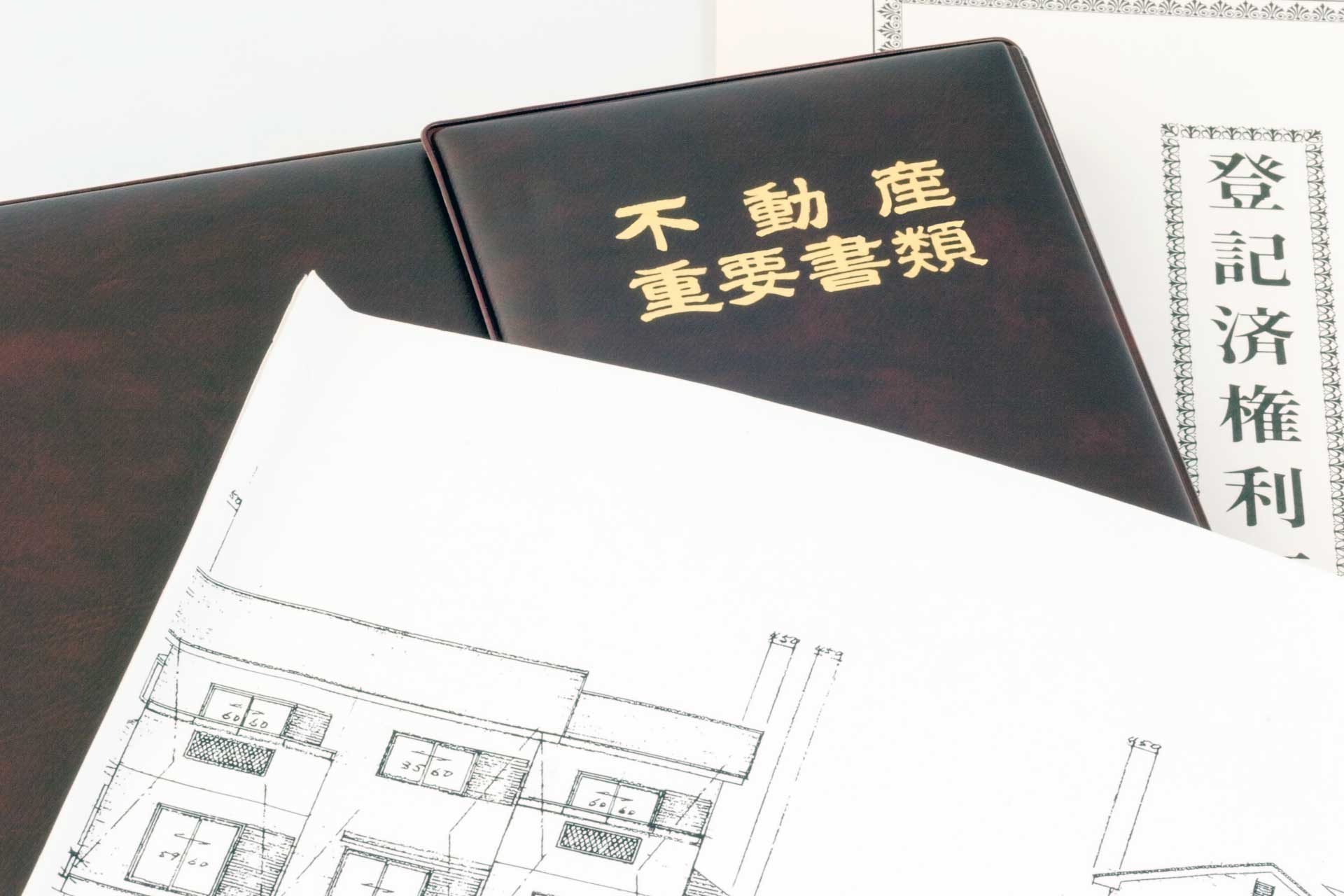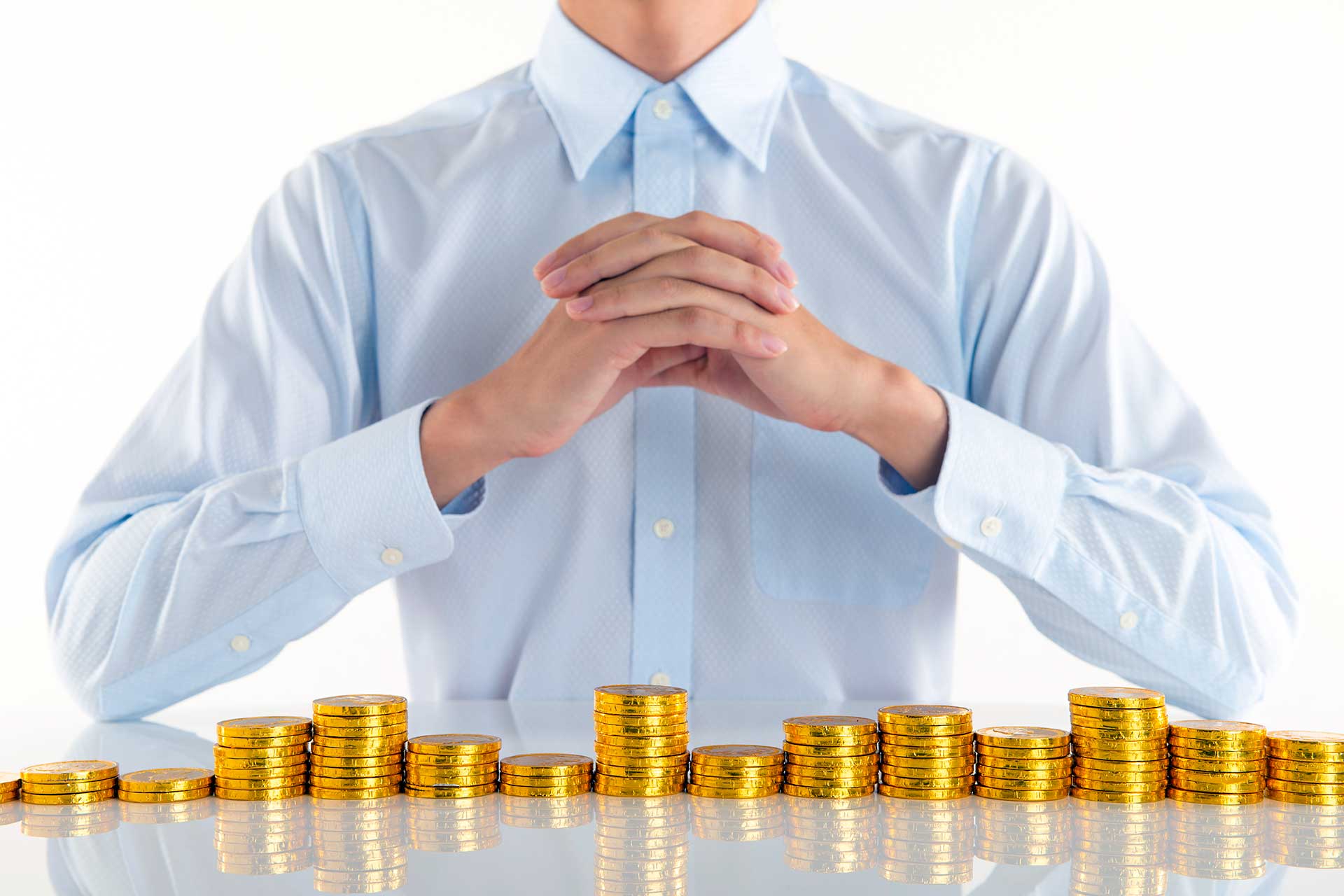遺産分割とは
被相続人が死亡した際、死後の財産の分配について遺言が残されていない場合、相続開始(被相続人の死亡)と同時にその財産は相続人全員で共有している状態となります。
遺産分割を行わず、全ての遺産を相続人全員の共有財産として残しておくことも可能ですが、共有のままではその財産の管理や運用に支障を生じ、将来もめ事の原因となりかねません。
それを未然に防ぐためにも、相続が発生した際は早期に遺産分割の協議をして個々の遺産を各相続人に配分しておくのが賢明です。
このように相続財産を誰が取得するか決めて相続人間で分配することを遺産分割といいます。
遺産分割を行う際には、相続人が全員で分割協議を行う必要があります。
一般的には、自宅は配偶者、事業権などがある場合は事業を継承するべき相続人(長男など)が相続するケースが多いようです。
また、ほとんどの財産を配偶者に相続させるケースもあります。
配偶者の税額軽減の枠までは相続税が0になるので、一見税金面でもお得です。ただ、長い目で見ると、早い段階で財産を次の世代に移しておいた方が得な場合もあります。例えば、お父様が亡くなってお母さまが遺産の多くを相続されたような場合、お母さまご自身が既にお持ちの財産と相続で取得された財産を合わせると、次の相続のときに納める税金が極めて多額になってしまうということもあり得ます。