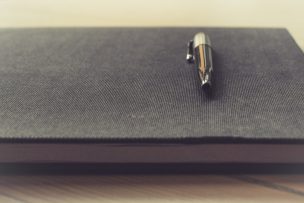租税特別措置法40条の要件
個人が、土地、建物、株式などの財産を法人に寄附(法人に対する贈与若しくは遺贈又は法人を設立するための提供をいいます。) をした場合には、寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税 されます* (所法59①一)。
*これは、個人から法人に土地、建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を清算する必要があるためです。
ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が「一般特例」 又は「承認特例」 の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」 )を受けたときは、所得税を非課税 とする制度があります(措法40①後段)。
この非課税制度には「一般特例」と「承認特例」の二つが有り、対象となる法人の種類や承認要件が異なります。
制度の種類 一般特例 承認特例 対象となる法人 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人*1 、その他の公益を目的とする事業を行う法人(社会福祉法人、学校法人、宗教法人、NPO法人など) 公益法人等のうち、国立大学法人等*2 、公益社団法人、公益財団法人、学校法人*3 、社会福祉法人及び認定NPO法人等*4 承認要件 次の要件を全て満たすこと*5 次の要件を全て満たすこと*6 要件1 要件1 要件2 要件2 要件3 要件3 自動承認 なし*7 あり
*1「特定一般法人」とは、一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法に掲げる一定の要件を満たすものをいいます。
*2「国立大学法人等」とは、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいい、国立大学法人等のうち法人税法別表第一に掲げるものを「特定国立大学法人等」といいます。
*3 私立学校振興助成法第14条第1項に規定する学校法人で学校法人会計基準に従い会計処理を行うものに限ります。
*4「認定NPO法人等」とは、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいいます。
*5 法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人などに対する寄附である場合の一般特例の承認要件は、要件2のみになります。
*6 特定国立大学法人等に対する寄附である場合の承認特例の承認要件は、要件2及び要件3となります。
*7 博物館等を運営する独立行政法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人並びに博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人をいいます。)に対する寄附について、次の事項を証明する文部科学大臣の書類を添付した承認申請書の提出があった場合において、その承認申請書の提出があった日から一ヶ月以内にその申請について非課税承認が無かったとき、又は非課税承認をしないことの決定が無かったときは、その申請について非課税承認があったものとみなされます(措令25の17⑧一)。
その寄附財産が、一定の有形文化財(建造物等を除く。)に該当すること
その寄附財産が、その寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、その寄附を受けた独立行政法人等の公益目的事業(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律に基づく認定を受けた一定の事業としてその認定を受けた独立行政法人等が有する文化観光拠点施設において行うも荷に限ります。)の用に直接供され、又は供される見込であること
一般特例と承認特例
一般特例は、公益法人等に財産を寄附 した場合に、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなどの要件を満たすものとして非課税承認 を受けたときは、この寄附に対する所得税を非課税 とする制度です(措法40①後段)。
承認特例は、承認特例対象法人 に財産を寄附した場合に、寄附した人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等に該当しないなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときは、所得税を非課税 とする制度です。申請書を提出した日から1か月 (「特定国立大学法人等」 以外の承認特例対象法人に対する一定の株式等の寄附の場合には、3か月 )以内にその申請について非課税承認がなかったとき、又は承認しないことの決定がなかったときは,その申請について非課税承認があったものとみなされます(自動承認) 。
承認要件
一般特例
一般特例に係る非課税承認を受けるためには、要件1から要件3の全ての要件 を満たすことが必要です。(措令25の17⑤一,二,三)なお、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人 、国立大学法人 などに対する寄附である場合には、要件2のみ です。
要件1
寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
【具体的な判定基準】
次の1~4までの全てを満たしているときは、要件1に該当するものとされます。
寄附を受けた公益法人等のその寄附に掛かる公益目的事業が、その事業の内容に応じ、その公益目的事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有すること
寄附を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益が、それを必要とする人の現在又は将来における勤務先、職業などにより制限されること無く、公益を必要とする全ての人に与えられるなど公益の分配が適正に行われること
寄附を受けた公益法人等のその寄附に係る公益目的事業について、その公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大で無いことその他その公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実が無いこと
寄附を受けた公益法人等の事業の運営について、法令に違反する事実その他公益に反する事実が無いこと
要件2
寄附財産(代替財産を含む*1 )が、寄附日から2年を経過する日までの期間*2 内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込であること
*1「代替資産」とは、収容や災害など一定のやむを得ない理由により寄附財産を譲渡した場合に、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した減価償却、土地、土地の上に存する権利及び株式(株式にあっては、株式交換など一定のやむを得ない理由により寄附財産である株式を譲渡したことにより取得したものに限ります。)などをいいます。
*2「2年を経過する日までの期間」については、例えば、寄附を受けた土地の上に建物を建設し、その建物を公益目的事業の用に直接供する場合において、その建物の建設に要する期間が通常2年を越えるときなど、一定のやむを得ない事情があるため、寄附財産を寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難であると認められるときは、その期間については国税庁長官が認める日までの期間となります。
要件3
寄附により、寄附をした人の所得税又は寄附をした人の親族等の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること
【具体的な判定基準】
次の1~5までの全てを満たしているときは、要件3に該当するものと認められます。
1)寄附を受けた公益法人等の運営組織が適正であると共に、その寄附行為、定款又は規則(以下「定款等」という。)において、理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)のうち親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人(以下「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること
(注)「理事、監事及び評議員」には、名称の如何を問わず実質的に見てこれらと同様の役職(例えば、宗教法人の「責任役員」など)も含まれます。
「運営組織が適正である」とは
運営組織が適正であるかどうかの判定は、次に掲げる事実が認められるかどうかによります。
定款等において、一定の事項が定められていること
寄附を受けた公益法人等の事業の運営及び役員等の選任などが、法令及び定款等に基づき適正に行われていること
寄附を受けた公益法人等の経理については、その公益法人等の事業の種類及び規模に応じて、その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正に記帳されていると認められること
「特殊の関係がある人」とは
特殊の関係がある人とは、次に掲げる一定の関係を有する人を言います。
その人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人
その人の使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人
1又は2に掲げる人の親族でこれらの人と生計を一にしている人
以下に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員又は使用人
その人が会社役員となっている他の法人
その人及び1~3までに掲げる人並びにこれらの人と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
2)寄附をした人、寄附を受けた公益法人等の役員若しくは社員又はこれらの人の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと
3)寄附を受けた公益法人等の定款において、その公益法人等が解散した場合の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること
4)寄附を受けた公益法人等につき公益に反する事実が無いこと
5)寄附により公益法人等が株式の取得をした場合には、その取得によりその公益法人等の保有することとなるその株式の発行法人の株式(寄附前から保有する株式を含む。)が、その発行済株式の総数の2分の1うぃ越えないこと
承認特例
承認特例に係る非課税承認を受けるためには、要件1から要件3まで全ての要件 (特定国立大学法人等に対する寄附 である場合には、要件2及び要件3に掲げる要件 )を満たすことが必要です(措令25の17⑦一,二,三)。
要件1
寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等及び社員※ 並びにこれらの人の親族等に該当しないこと
※「社員」とは、公益社団法人などにおける社員総会を構成する人をいい、いわゆる従業員とは異なります。
要件2
寄附財産について、一定の基金若しくは基本金に組み入れる方法により管理 されていること又は不可欠特定財産 に係る必要な事項が定款で定められていること
国立大学法人等の場合
寄附財産が、研究開発の実施等の公益目的事業に充てるための基金に組み入れる方法(基金が公益目的事業に充てられることが確実であることなどの一定の要件を満たすことについて、寄附を受けた法人が所管庁の証明を受けたものに限ります。)により管理されていること
公益社団法人・公益財団法人の場合
次の(a)又は(b)のいずれかの方法 によります。
(a)寄附財産が、寄附を受けた法人の不可欠特定財産 ※ であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること
※「不可欠特定財産」 とは、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産をいい、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、その法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をいいます。例えば、一定の目的の下で収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化価値があり、再生不可能な建造物等が該当します。
(b)寄附財産が、一定の公益目的事業に充てるための基金に組み入れる方法 ※ により管理されていること
※上記の国立大学法人等の場合と同様です。
学校法人の場合
寄附財産が、寄附を受けた法人の財政基盤の強化を図るために、学校法人会計基準第30条第1項第1号から第3号までに相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法により管理 されていること
社会福祉法人の場合
寄附財産が寄附を受けた法人の経営基盤の強化を図るために、社会福祉法人会計基準第6号第1項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法により管理されていること
認定NPO法人等の場合
寄附財産が、一定の特定非営利活動に係る事業に充てるための基金に組み入れる方※ により管理されていること
※上記の国立大学法人等の場合と同様です。
要件3
寄附を受けた法人の理事会等において、寄附を申し入れること及び寄附財産について基金若しくは基本金にの組み入れ又は不可欠特定財産とすることが決定されていること
承認特例の適用を受けるための必要書類
承認特例の適用を受けるためには、以下の添付書類を添付した申請書等を承認申請書の提出期限までに提出する必要があります(措令25の17⑦)。
申請書等
承認申請書「第1表」、「第2表」、「第3表(承認特例用)」(「第3表ー付2」を含む。)、「第5表」及び「第6表」
承認申請書各表における必要な書類
承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書
贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しない旨の誓約書、贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを確認した旨の証明書
*特定国立大学法人等に対する寄附の場合は不要。
添付書類
次の事項の記載のある寄附を受けた法人の理事会等の議事録の写し
寄附の申出を受け入れることを決定した旨
寄附財産について基金若しくは基本金に組み入れること又は不可欠特定財産とすることを決定した旨
その決定に係る財産の種類、所在地、数量などの事項*
*議事録に3の事項が記載されていない場合は、1及び2の事項の記載のある理事会等の議事録の写しと3の事項が記載された書類。
国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人* 又は認定NPO法人等に対する寄附の場合
基金に組み入れる方法により管理することを証する所轄庁の証明書の写し
*寄附財産を基金に組み入れる方法により管理している公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
「承認特例」に係る非課税承認を受けた人が提出しなければならない書類
「承認特例」に係る非課税承認を受けた人(寄附をした人)は、寄附を受けた法人の区分に応じ、その寄附をした日の属する事業年度において、寄附財産について、基金若しくは基本金に組み入れる方法により管理されたこと又は不可欠特定財産とされたことが確認できる以下の書類を、その事業年度終了の日から3ヶ月以内(その期間の経過する日後に承認申請書の提出期限が到来する場合には、その提出期限まで)に、所得税の納税地を所轄する税務署に提出する必要があります(措令25の17⑨)。
この書類が提出すべき期限までに提出されなかった場合、非課税承認が取り消されます。
寄附を受けた法人の区分 書類 国立大学法人 基金明細書の写し 公益社団法人 (寄附財産を不可欠特定財産とした場合) (寄附財産を基金に組み入れた場合) 学校法人 基本金明細表などの写し 社会福祉法人 基本金明細書などの写し 認定NPO法人等 基本金明細書の写し
非課税承認の取消
非課税承認を受けた後であっても、寄附財産が、寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなった場合等には、国税庁長官は、その非課税承認を取り消すことが出来ることとされています(措法40②③)。
非課税承認が取り消された場合には、その取り消されることとなった事実の内容に応じ、寄附をした人又は寄附を受けた公益法人等に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。
【非課税承認が取り消される例】
課税対象者 取り消される場合 寄附をした人 「承認特例」に係る非課税承認を受けた人が、寄附財産について、基金若しくは基本金に組み入れる方法により管理されたこと又は不可欠特定財産とされたことが確認できる書類を、提出すべき期限までに提出しなかった。 寄附財産が寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなかった。 寄附を受けた公益法人等 寄附財産が寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなった。
租税特別措置法40条後段の承認の対象となる資産
国税庁長官の承認申請の対象となる譲渡資産は次のとおりである。
山林(事業所得の基因となるものを除く)
山林とは販売を目的として伐採適齢期まで相当長期間にわたり管理育成を要する立木の集団をいう。販売を目的として育成している立木や苗木は、事業所得の棚卸し資産となり山林に該当しない。
譲渡所得の基因となる資産
譲渡所得の基因となる資産は、棚卸し資産、棚卸し資産に準ずる資産、山林及び金銭債権以外の一切を資産をいう。金銭債権は譲渡所得の基因となる資産ではないのでみなし譲渡の対象となる資産には該当しない。金銭債権の譲渡により生じた利益は、元本価値の増加というよりは金利に相当するものであると考えられているからである。借地権の設定は含まず、借地権の無償返還は59条の対象となる場合がある(注) 。国外にある土地、借地権等、建物、附属設備、構築物を除く(措法40①、措令25の17②)。
(注)所得税基本通達59-5《借地権等の設定及び借地の無償返還》。所得税法59条1項に規定する「譲渡所得の基因となる資産の移転」には、借地権等の設定は含まれないのであるが、借地の返還は、その返還が次に掲げるような理由に基づくものである場合を除き、これに含まれる(昭56直資3-2、直所3-3追加)。
借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること。
当該土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用していたものであること。
借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。
有価証券の譲渡による所得のうち、公社債等の譲渡による所得は非課税(措法37の15)となるが、それ以外の有価証券を不お陣に贈与又は遺贈した場合には、原則として承認申請の対象となる。
(注)平成28年1月以降は、公社債等に対する課税方式が、上場株式等と同様、税率が20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離方式に変更された上で、公社債等の譲渡所得が非課税から課税とされる一方、上場株式等と損益通算できる範囲が公社債等にまで拡大される。この結果、平成28年1月以降は、全ての有価証券につき、原則として承認申請の対象となる。
租税特別措置法37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
公社債(第37条の10第2項第3号に規定する新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに第8条の2第1項第2号に規定する社債的受益権(次項第1号において「公社債等」という。)の譲渡(所得税法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号に定める事由によるものを除く。次項第1号において同じ。)による所得
公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第2号において「子公社債投資信託等」という。)の終了又は公社債投資信託等の一部の解約によりその公社債投資信託等の受益権(特定目的信託の受益権については、第8条の2第1項第2号に規定する社債的受益権に限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第9条第1項第11号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第2号において同じ。)のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
次に掲げる金額は、所得税法の規定の適用については、ないものとみなす。
公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
前項第2号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益権を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
租税特別措置法37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》
次に掲げる所得については、前条第1項の規定は、適用しない。
割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡した事による所得として政令で定めるもの
利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡した事による所得として政令で定めるもの
国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるものを譲渡した事による所得として政令で定めるもの
利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡した事による所得として政令で定めるもの
前項各号に規定する公社債の譲渡については、前条第2項の規定は、適用しない。
租税特別措置法40条の適用を受けるための承認要件
国税庁長官の承認を受けるための一定の要件(承認要件)は、次のとおりである(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(介護老人保健施設、公立大学など一定のもの)などに対する寄附である場合には、【承認要件2】を具備すれば足りる)。(措令25の17⑤)。また、私立学校法人助成法に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対する贈与、遺贈については別途異なる要件が定められている(措令25の17⑦、措規18の19④)。
承認要件1
贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すること(措令25の17⑤一)
この要件は、公益を目的とする法人に対する贈与又は遺贈で、公益の増進に著しく寄与する贈与又は遺贈であるかどうかにより判定するが、公益法人等の事業活動が次の1から4までの全てに該当するときは、この要件を満たすものとして取り扱われる(租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて:例規通達:昭和55年4月23日直資2-181(以下、「40条通達」という。))。なお、贈与、遺贈が法令の規定に違反したものであるときは、この要件を満たさないこととされている(40条通達11)。
1.公益目的事業の規模
受贈法人が営む公益時報の規模が事業の内容に応じ、その事業を営む地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有すること。なお、たとえば、学校教育法や社会福祉法に規定する一定の事業、宗教の普及や信者の教化育成に寄与する事業、30人以上の学生等に対して学資の支給若しくは貸与を行う事業又は科学技術その他の学術に関する研究者に助成金を支給する事業などが受贈法人の主たる目的として行われる場合には、その公益目的事業は社会的存在として認識される程度の規模を有するものとして取り扱われる(40条通達12(1))。
2.公益の分配
受贈法人の事業の遂行により与えられる公益の分配は、特定の者に限られることなく、適正に行われていること(40条通達12(2))。
3.事業の営利性
贈与又は遺贈を受ける法人の公益目的事業について、公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないこと、その他当該事業の経営が営利企業的に行われている事実がないこと(40条通達12(3))。
4.法令の遵守等
受贈法人の事業の運営につき、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと(40条通達12(4))。
承認要件2
贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内(贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設する当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供する建物の建設に要する期間が通常2年を越えることその他やむを得ない事情があるため、当該期間内に財産の贈与又は遺贈を受けた法人の事業の用に供することが困難である場合には、国税庁長官が認める日までの期間)に、財産を受けた法人の贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に直接供され又は供される見込であること(措法40①、措令25の17⑤二)
公益法人に贈与・遺贈された財産は、その贈与を受けた公益法人が直接、公益を目的とする事業の用に供さない場合には非課税とされない。ただし、次に挙げるやむを得ないと認められる理由がある場合に限り、その贈与に係る財産の譲渡を認めることとされている(措令25の17③)
贈与・遺贈された財産を収用や換地処分などにより譲渡する場合
贈与・遺贈された財産で公益目的事業の用に直接供する施設につき、災害、震災、風水害、火災等があった場合において、その復旧を図るためにその財産を譲渡する場合
贈与又は遺贈により取得した財産を直接公益目的事業に供している施設における公益目的事業の遂行が①公害や周辺において行われるキャバレー、ナイトクラブなどの営業により著しく困難となった場合、または、②施設の規模を拡張する場合において、施設の移転をするために施設を譲渡する場合
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、制作、建築をする場合において、その費用に充てるため贈与又は遺贈を受けた財産を譲渡する場合
その他これに準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由、また、公益法人が贈与に係る財産をやむを得ない理由で譲渡した場合であっても、この譲渡による収入金額の全部に相当する金額を持って代替資産(減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)を取得しなければ、この特例の適用が受けられないこととされている(措法40②、措令25の17③、措規18の19③)。
なお、株式、著作権などのように、財産の性質上その財産を直接公益事業に供されないものは、毎年の配当金、印税収入などその財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかにより、その財産が当該公益事業の用に供されるかどうかを判定して差し支えないものとされている。この場合において、各年の配当金、印税収入などの果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかは、たとえば、学校援護法人によって学資として支給され、研究助成を行う法人によって助成金として支給されるなど、果実の全部が直接、かつ、継続して、公益事業の用に供されるかどうかにより判定される(40条通達13)。
なお、次のような使い方は寄贈された財産が公益事業に使われているとはいえないとされていることに注意が必要である。
建物を賃貸の用に供し、当該賃貸にかかる収入を公益事業の用に供する場合
配当金などの果実が毎年定期的に生じない株式等
承認要件3
公益法人に財産を贈与又は遺贈することにより、贈与者・遺贈者の所得税の負担を不当に減少させ贈与者・遺贈者又はその親族等の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと(措令25の17⑤三)
次の要件(1~4)を満たすときには、贈与者・遺贈者の所得税の負担を不当に減少させ又は贈与者・遺贈者又はその親族等の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められる(措令25の17⑥)。また、受贈法人の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずる者や職員の中に、贈与・遺贈した者又はこれらの者と親族その他特殊関係がある者が含まれておらず、かつ、これらの者が受贈法人の財産の運用及び事業の運営について私的に支配している事実がなく、将来においても私的に支配する可能性がないと認められる場合には、次の2から4までの要件に該当していれば、所得税又は想像税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるとして取り扱われる(40条通達17ただし書き)。
組織運営が適正であり、役員等のうち親族等の数が3分の1以下と定められていること(措令25の17⑥一)。
贈与者・遺贈者、受贈法人の役員等若しくは社員又はそれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと(措令25の17⑥二)。
寄附行為、定款又は規則において、受贈法人解散後の残余財産は、国、地方公共団体又は他の公益法人に帰属する旨の定めがあること(措令25の17⑥三)。
受贈法人につき公益に反する事実がないこと(措令25の17⑥四)
私立学校法人特例
平成15年の税制改正で、私立大学等を設置する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る国税庁長官の承認手続等の特例が次のとおり創設された。
その贈与又は遺贈が、法律の規定により自主的にその財政基盤の強化を図るべき事とされている私立大学等を設置する学校法人で文部科学省の定める基準に従い会計処理を行う者に対する者である場合の国税庁長官の承認要件は次に掲げる要件とすることとされた(措令25の17⑦、措規18の19④~⑨)。
贈与又は遺贈(以下、「寄附」という。)をした者が、寄附を受ける学校法人の理事、監事及び評議員並びにその親族等に該当しないこと
寄附財産(寄附財産を譲渡した場合には、その譲渡による収入の全額又はそれによって取得した財産を含む。)が、寄附された学校法人において学校法人会計基準30条1号から3号までの基本金に組み入れて管理されていること
寄附の受入れ及び当該寄附財産の基本金への組入について理事会において決定されていること
この結果、私立大学等(私立学校振興助成法に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人)に贈与又は遺贈したケースならば、受贈者たる私立大学法人等は、受贈財産をいったん、基金に組み入れた後に譲渡し、譲渡代金を基金に組み入れることにより租税特別措置法40条の要件を満たすこととなる。国立大学法人では、この規定がないので、国立大学法人に対し現物資産を贈与又遺贈する場合には、譲渡所得の課税対象となる可能性が高いことに留意する必要がある。
平成15年4月28日付で文部科学省私学部長通知「文部科学大臣所轄学校法人への現物寄附に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和等について(通知)15文科高第103号」が発遣されている。以下の記載は主に同通達による。
平成15年4月1日より文部科学大臣所轄学校法人に対する現物寄附について、国税庁長官の承認を受けるための要件が緩和されると共に、手続が簡素化された。今般の変更点については下記の通りで有る。
a 私立学校法人助成法に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対する現物寄附については、国税庁長官の承認を受けるための申請書にbの書類を添付することにより、承認要件を次のとおりとすることができる。
寄附をした者が、寄附を受ける学校法人の理事、監事又は評議員並びにその親族等に該当しないこと
寄附財産(当該寄附財産を譲渡した場合には、その項とによる収入の全額又はそれによって取得した財産を含む。)が、寄附された学校法人において学校法人会計基準第30条第1号から第3号までの基本金に組み入れられていること
寄附の受入れ及び寄附財産の基本金への組入について理事会において決定されていること
ただし、申請書の提出時に1の要件に該当していなかった場合、又は申請書の提出時に1の要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、提出後aの要件に該当しないこととなった場合には、租税特別措置法第40条第2項に基づき承認が取り消されることがある。
b この特例を受けるために、寄附者が国税庁長官の承認を受けるための申請書には、寄附を受ける学校法人から交付された次の書類を添付する必要があること。
寄附をした者が寄附を受ける学校法人の理事、監事及び評議員並びにその親族等に該当しないことについて寄附者が誓約した旨及び寄附をした者が寄附を受ける学校法人の理事、監事及び評議員並びにその親族等に該当しないことについて寄附を受ける学校法人において確認した旨を記載した書類
寄附の受入れ及び寄附財産の基本金への組入について理事会において決定されていることを証明するための議事録その他これに相当する書類の写し及び決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類
c この特例を受けて国税庁の承認を受けた場合には、寄附を受けた事業年度に寄附財産を基本金に組み入れたことを確認できる基本金明細表を、当該事業年度終了日以後3ヶ月以内に税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならず、この提出がない場合には、租税特別措置法40条第2項に基づき承認が取り消されることがあること。
したがって、基本金明細表の作成にあたっては、この特例を受けた寄附財産が明確になるよう、この特例を受ける資産である旨を摘要の欄に記載すること。
d この特例を受けるためには、譲渡を予定している場合であっても、寄附を受けた財産について一旦基本金に組み入れることが必要であり、その旨の決定がb2の議事録に掲載されている必要があること。なお、「寄附の受入れ」、「基本金への組入」、「譲渡の決定」、「譲渡により取得した資産の基本金への組入の決定」を同時に行うことは可能であり、その旨の決定を理事会において行う必要があること。
e 一旦基本金に組み入れた寄附財産について、国税庁長官の承認を受けた後に、譲渡及び譲渡による収入により取得した財産を基本金に組み入れる際に、改めて国税庁長官の承認を得る必要はないこと。ただし、基本金の管理状況を記録しておくため、当該決定に係る議事録は作成しておく必要があること。
f 上述bの書類を添付した申請書の提出があった場合において、提出の比からヶ月以内に承認又は承認をしない旨の決定がなかった場合には、承認があったものとみなされること。このため、申請の期限(寄附後4ヶ月以内)を厳守すると共に、下記申請書及び添付書類について遺漏の内容にする必要がある。
g この特例を受ける場合に、提出すべき申請書及び添付書類(bに掲げる書類を含む。)は図表Ⅳ-1の通りであり、下記に記載のない各表等は、原則として不要である。
図表Ⅳ-1 私立学校法人特例申請書・添付書類一覧表
表番号 内容 添付書類 第1表 寄附者の住所、氏名、生年月日、職業等 寄附者が死亡している場合、寄附者と申請者の関係(親子等)が確認できる戸籍謄本 第2表 寄附を受けた学校法人の設立年月日及び事業の目的・寄附の目的 学校法人の登記簿謄本 第3表 寄附財産の明細及び使用目的 寄附を申し込んだ事実が確認できる書類(寄附申込書、遺言書の写し等) 第5表 理事、監事及び評議員の氏名及び寄附者との関係 理事、監事及び評議員の名簿(住所が分かるもの。第5表、第6表の「住所」の欄に記載があれば添付は不要。) 第18表 添付書類一覧表
その他
法人の機関の構成と親族等制限規定
Q 公益財団法人の理事(10名)に、財産の寄附者と寄附者が代表取締役を務める株式会社の役員2名及びその従業員1名が含まれていますが、この場合、受贈法人の理事の構成は親族等制限規定に抵触することになりますか。
A 受贈法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触するかどうかの判定は、役員等とその親族等の合計数が、それぞれの役員等の数の3分の1以下であるかどうかにより行われることとなりますが、この場合の親族等は、親族及びその者と特殊の関係があるものを指し、特殊の関係があるものには、理事が役員となっている他の法人の役員や使用人などが含まれます。
したがって、照会の場合、受贈法人の理事に、財産の寄附者と寄附者が代表取締役を務める株式会社の役員2名及びその従業員1名が含まれており、親族等の関係を有するものの合計数が4名となることから、理事の構成が親族等制限規定に抵触することになります。
国税ホームページ質疑応答事例
【関連法令通達】
国税庁長官の承認取消が有った場合の譲渡所得の課税について
イ 次の承認取消事由に該当する場合は、贈与又は遺贈した個人に譲渡所得、山林所得又は雑所得が課税される(措法40②、措令25の17⑩⑫)。課税年分は、非課税承認が取り消された日の属する年分(その日までに贈与をした者が死亡していた場合には、その死亡の日の属する年分)又は遺贈のあった日の属する年分とされている(措法40②、措令25の17⑩⑫)。
2年を経過する日内に公益法人等に贈与又は遺贈された財産又は代替財産が公益目的事業の用に直接供されなかったとき
公益目的事業の用に直接供される前に不当減少要件に該当することとなったとき
学校法人に対する非課税承認を受けた者が学校法人会計基準の基本金への組入が有ったことを確認できる書類を事業年度終了の日から3ヶ月以内に提出しなかったこと
ロ 次の承認取消事由に該当する場合は、贈与又は遺贈を受けた法人を個人とみなして譲渡所得、山林所得又は雑所得が課税される(措法40③、措令25の17③、措規18の19⑩)。課税年分は、非課税承認が取り消された日の属する年分(その日までに贈与をした者が死亡していた場合には、その死亡の日の属する年分、遺贈があった場合には遺贈のあった日の属する年分)とされる(措法40③後段、措令25の17⑮)。
贈与又は遺贈を受けた財産を公益目的事業の用に直接供しなくなったこと
公益目的事業の用に直接供された後に不当減少要件に該当することとなったとき
学校法人特例の申請書の提出時において、贈与・遺贈をした者が公益法人等の役員及び親族等に該当しないことという要件に該当していなかったこと及び提出時において要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、提出後に要件に該当しないこととなったこと
非課税承認の取り消し
Q 特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に土地を寄附し、その土地を社会福祉法人が特別養護老人ホームの敷地として使用していましたが、社会福祉法人の規模縮小に伴い、その特別養護老人ホームが閉鎖され、土地は貸駐車場として使用されています。
この場合、租税特別措置法第40条の非課税承認が取り消され、所得税が課税されることとなりますか。
A 受贈法人が、租税特別措置法第40条の非課税承認に係る寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供しなくなったなど一定の事実が生じた場合には、非課税承認が取り消されることとなります。
この場合、受贈法人が寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供する前に非課税承認が取り消されたときは、寄附者に対して所得税が課税されますが、公益目的事業の用に直接供した後に非課税承認が取り消されたときは、受贈法人に対して所得税が課税されます。
したがって、照会の場合は、受贈法人が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に非課税承認が取り消されることになりますので、受贈法人に対して所得税が課税されます。
国税ホームページ質疑応答事例
【関連法令通達】
非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
Q 租税特別措置法第40条の規定の適用を受ける寄附財産を受贈法人が譲渡し、その譲渡代金をもって他の資産を取得した場合、引き続きこの規定の適用が受けられますか。
A 受贈法人が、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けた寄附財産を譲渡した場合、次に掲げる要件を全て満たせば、引き続きこの規定の適用が受けられます。
1 譲渡する寄附財産は、受贈法人の公益目的事業の用に2年以上直接供していること。
2 寄附財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって他の資産(以下「買換資産」といいます。)を取得すること。
3 買換資産は、受贈法人の寄附財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる寄附財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利であること。
4 買換資産は、原則として、譲渡に日の翌日から1年を経過する日までの期間内に、受贈法人の公益目的事業の用に直接供すること。
5 受贈法人が、寄附財産の譲渡の日の前日までに、その譲渡の日など一定の事項を記載した書類を、受贈法人の所在地を所轄する税務署長に提出すること。
国税ホームページ質疑応答事例
【関連法令通達】
図表Ⅳ-2 個人から法人に対し贈与・遺贈が行われた場合
個人から法人に対し贈与・遺贈が行われた場合