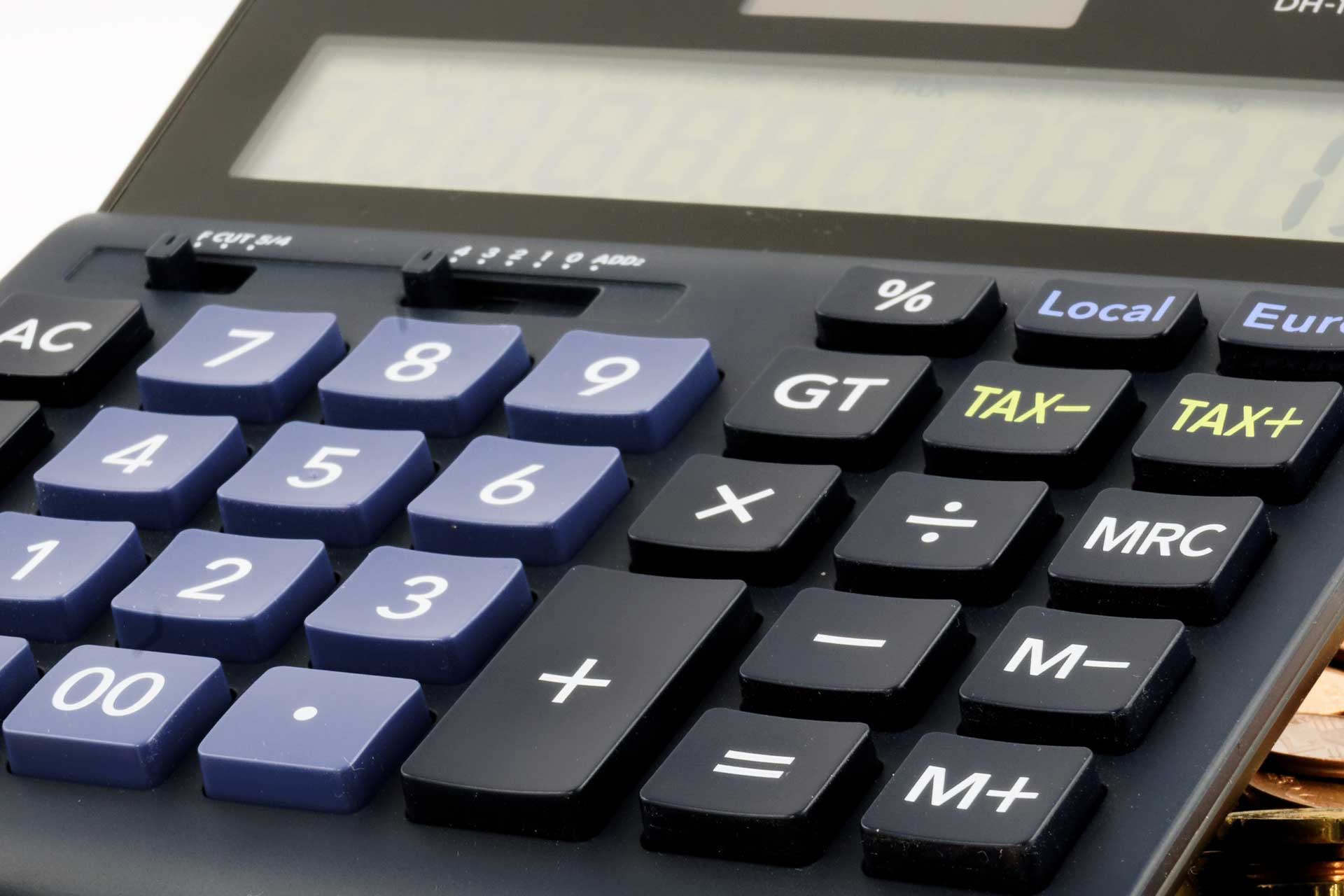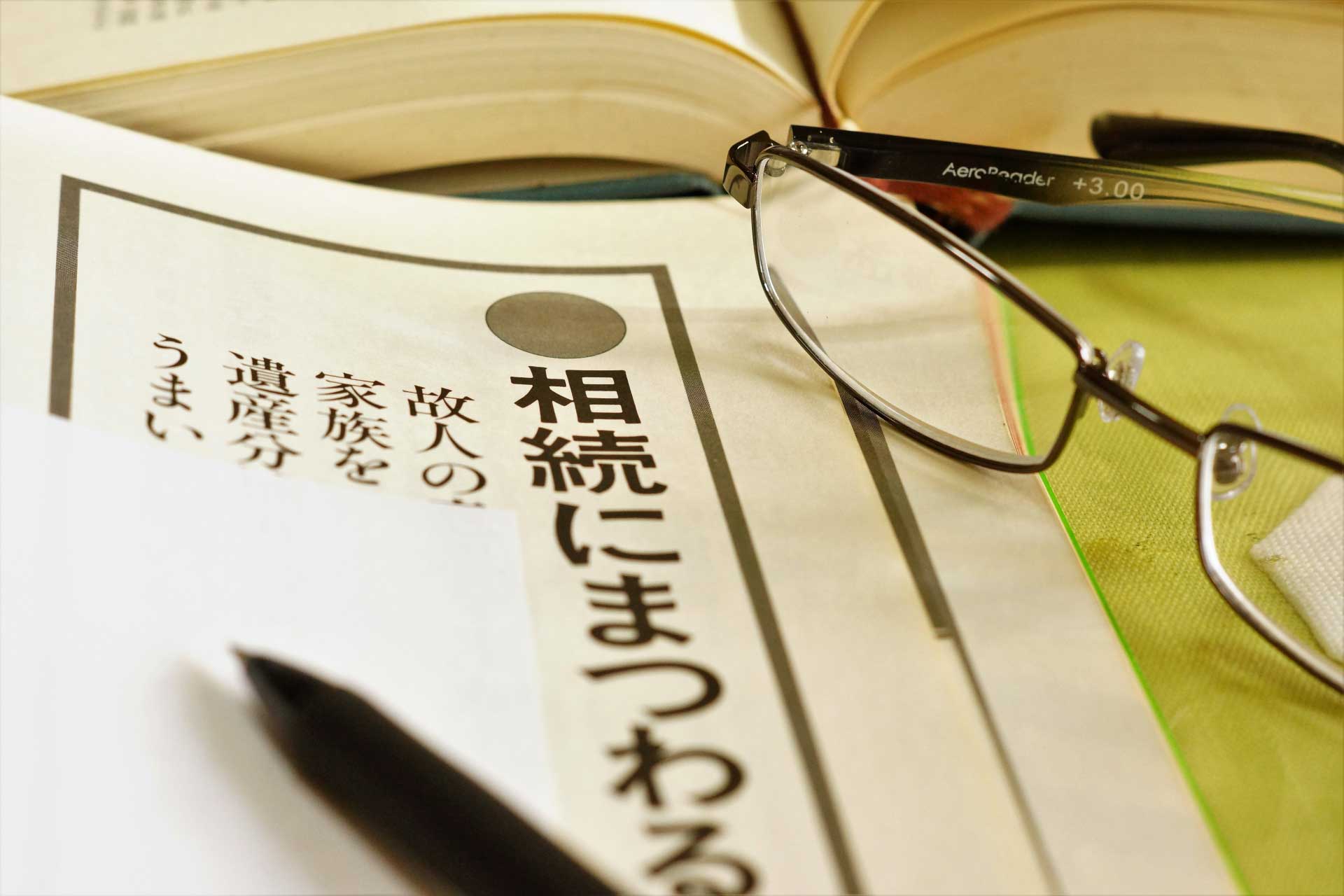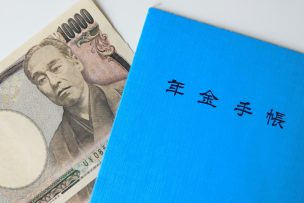被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係
(受遺者法人の態様別課税関係)
普通法人に遺贈した場合
- 普通法人は受贈益に対し法人税を負担する(法法22②)。
- 法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない(相法1の3)。
- 普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる(相法9、相基通9-2)。
- 遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される(被相続人に課税、準確定申告)(所法59①一)。
人格なき社団・財団に遺贈した場合
- 代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団(以下、「人格なき社団・財団」という。)は、個人とみなされ相続税が課税される(相法66①)。
- 人格なき社団・財団が公益を目的とする事業等を行っている等所定の要件を満たす場合、相続税は非課税となる(相法21の3①三)。
- 相続税が課税される場合は、法人税等の額に相当する額を控除する(相法66⑤)。
- 遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される(被相続人に課税、準確定申告)(所法59①一)(人格なき社団・財団は法人とみなされている(所法4))。
持分の定めのない法人に遺贈した場合
- 寄附を受ける法人が34種の収益事業に対してだけ課税される法人の場合、法人税は非課税となる
- 寄附を受ける法人が全ての所得に課税される法人である場合は、受贈益は法人税の課税対象となる
- 原則、持分の定めのない法人には相続税は課税されないが、遺贈者の親族等の相続税の負担の不当な減少となる場合は持分の定めのない法人を個人とみなして相続税が課税される(相法1の3、66④)。その場合、法人税が課税された場合は、相続税から控除する(相法66⑤)。
利益を受ける者が親族等でなければ相続税法66条は適用されないので、同法65条により特別の利益を受ける者に相続税が課税される(相法65①)。 - 遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税される(被相続人に課税、準確定申告)(所法59①一)。遺贈を受ける法人が公益認定委員会により認定された公益社団法人、公益財団法人等、その他公益を目的とする事業を行う法人である場合には、遺贈の日から2年以内に公益目的事業に供するなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を得たときは、所得税法59条の1項1号の規定については遺贈がなかったものとみなすこととされている(措法40①後段)。承認の却下や取消の際は、遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税される(措法40②)。承認取消の際、法人が個人とみなされ譲渡所得の所得税課税を受ける場合もある(措法40③)。
図表Ⅵ-4 持分の定めのない法人の法人税の課税関係
| 分類 | 課税形態 |
|---|---|
| 法人税法別表第二掲載法人 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、社会医療法人、宗教法人など 公益社団・財団法人、公益認定委員会により公益認定された一般社団・財団法人 非営利型法人である一般社団・財団法人 | 34種類の収益事業課税 みなし寄付金特例 |
| 社会医療法人以外の財団である医療法人・持分の定めのない医療法人 その他の一般社団・財団法人 | 全所得課税 |
(注)持分の定めのない法人のうち財団である医療法人及び持分の定めのない社団である医療法人は、医療法に基づいて設立される医療法人である。社会医療法人以外の医療法人は、法人税法上、普通法人として取り扱われ原則として全所得課税されるが次の例外がある。
・設立時:資本金等の額の増加として扱われる。ただし、相続税法66条4項の規定により贈与税が課税された場合には、贈与税を控除した残額が資本金等の額となる(法法2①十六、22⑤、法令8①十四)。
・設立後:法人税課税(法法22②)
相談予約はこちらから