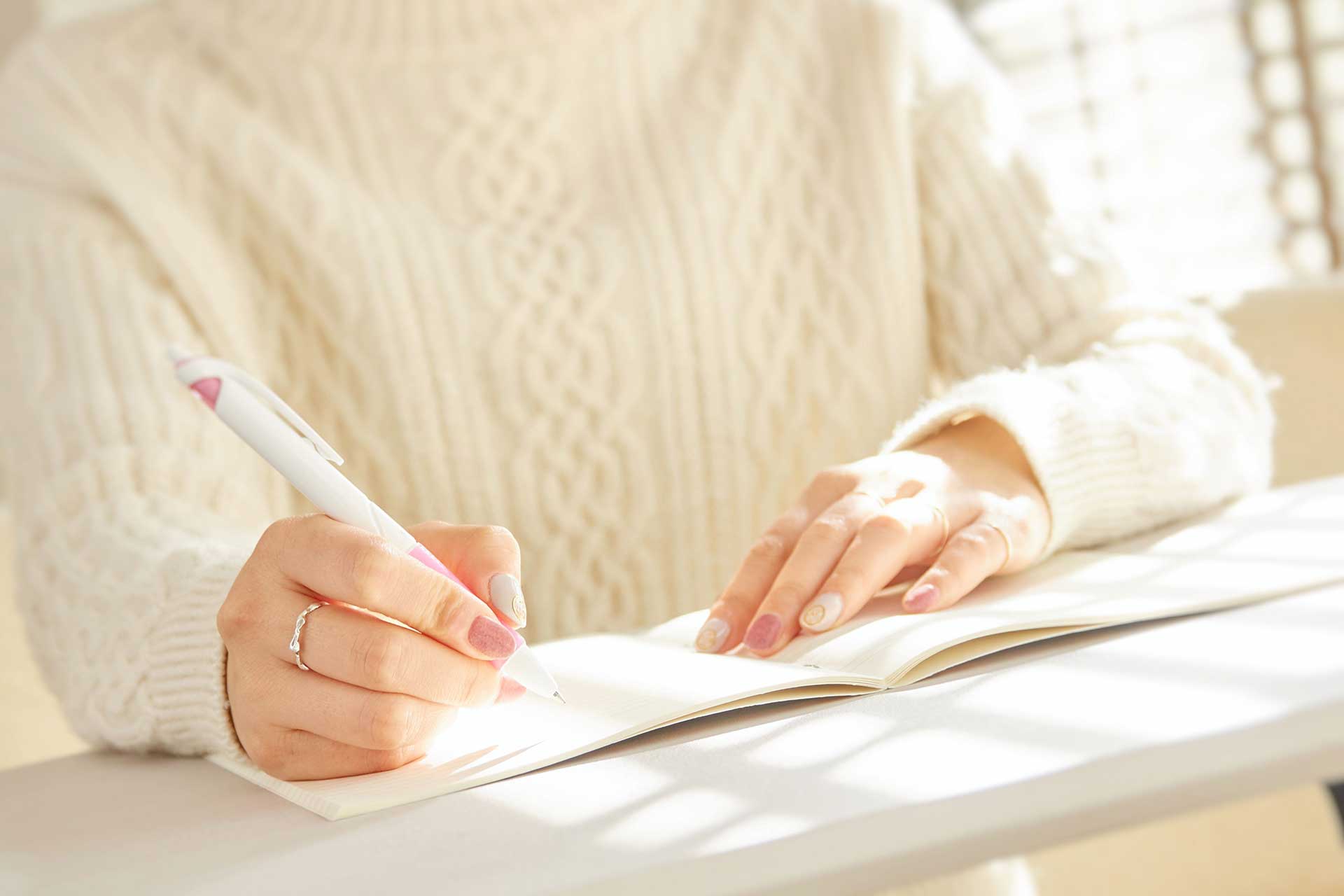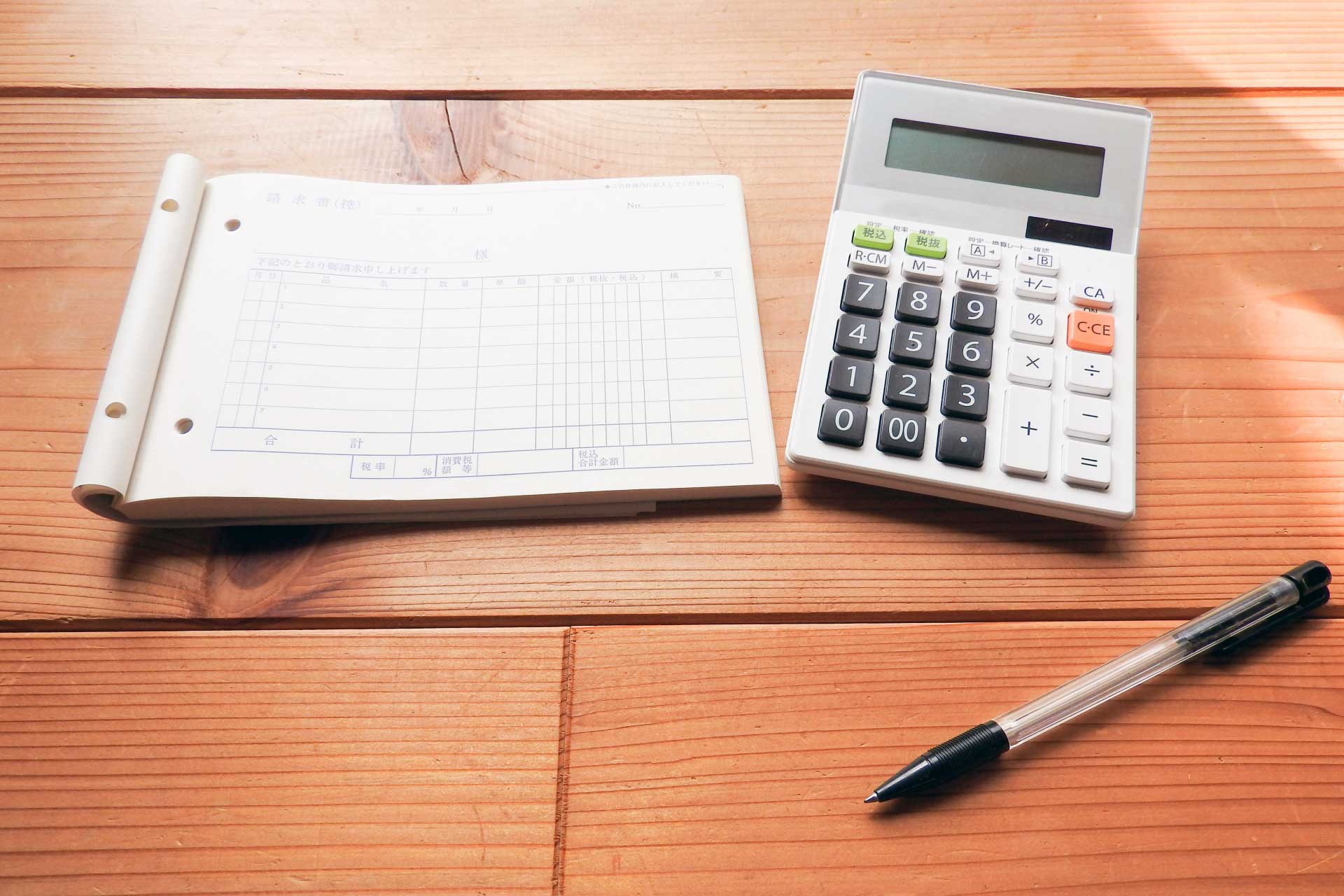相続税の申告の際、気を付けることは?
ポイントは4つです。
- 家族名義の相続財産
- 相続時精算課税
- 3年以内の贈与加算
- 債務等葬式費用
「家族名義」でも相続財産?
相続税の税務調査で申告漏れを指摘されやすいのが、家族名義になっている財産です。家族名義になっていても、実は被相続人(亡くなった方)の遺産とされる場合も少なくありません。
国税調査官はココを見ています
ご家族名義の預金通帳であっても、亡くなられた方の書斎や使っていた机の引き出し、金庫などに保管されていたものは、相続財産として認定される可能性が高くなります。家族名義の株式や投資信託についても同様で、運用内容によっては被相続人の財産として申告を求められる場合があります。名義預金や名義株として調査される可能性のある財産については、税理士法人日本税務総研の税理士によくご相談くださるようお願いします。
忘れていませんか、「相続時精算課税」の適用を受けた贈与財産
被相続人から生前に贈与を受け、相続時精算課税を適用した場合、その財産は相続税の課税対象財産になるというものです。贈与を受けた時から相続税申告までに年月を経て、うっかり忘れている方も多いので注意が必要です。相続時精算課税を適用したかが曖昧な場合、税務署へ問い合わせることも可能です。ひょっとしたらとお考えの方は当事務所の税理士にご相談ください。
贈与税の基礎控除以下でも加算される「相続開始前3年以内に贈与された財産」
被相続人の亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、たとえ贈与税の基礎控除以下であっても、相続税の課税対象に加算します。
贈与税の配偶者控除を適用した財産や、一定の住宅取得資金の贈与の特例を適用した財産は加算の対象になりませんが、資金の動きや支払内容を確認しておく必要があります。心当たりがある方は当事務所の税理士にお知らせください。
相続財産の価額から控除できる「債務と葬式費用」
控除できる債務
被相続人の債務で、次のようなものについては、相続財産の価額から差し引くことができます。
借入金
医療費・光熱費などの未払金
被相続人が亡くなられた日までに納めていなかった税金など
控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して、相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
お寺への支払い
葬儀社、タクシー会社への支払い
お通夜に要した費用など
Q私は、もしもの時に備えて、父(被相続人)が亡くなった当日までにATMで現金を引き出し、自宅に保管していました。このお金で病院や葬儀費用を支払っています。病院や葬儀費用に支払っているのでこのお金は申告しなくてもいいでしょうか?
A被相続人が亡くなった当日又は直前1か月ほどの間にATMで50万円ずつ何回も出金されているケースは珍しくありません。このような出金を税務署は必ずチェックします。不要な調査を受けないためにも、出金したお金が亡くなられた当日手元に残っている(ご自宅などに保管されている。)場合は、申告書に「手元現金」として遺産に計上します。その代わり、亡くなられた後に支払った病院の費用などは「(亡くなられた方の)未払金」、お布施などは「葬儀費用」として課税される財産から控除して申告書を作成します。
お任せください!当事務所のベテランの税理士がお手伝いします
相続税の申告手続きは複雑です。亡くなられた方の財産債務を漏れなく把握する必要があります。
税理士法人日本税務総研は、ベテランの税理士がお客さまお一人おひとりに入念なヒヤリングを実施した後に、その後の手続きが円滑に進むように、申告書の作成に必要な資料についてご説明いたします。
当事務所は弁護士、司法書士とも提携、総合サポートが可能です。
[ms_row]
[ms_column style=”1/3″ class=”” id=””]
[ms_flip_box direction=”vertical” front_paddings=”20″ front_background=”#bababa” back_paddings=”20″ back_background=”#828282″ class=”” id=””]
相続登記などが必要な方
|||
[/ms_flip_box]
[/ms_column]
[ms_column style=”1/3″ class=”” id=””]
[ms_flip_box direction=”vertical” front_paddings=”20″ front_background=”#bababa” back_paddings=”20″ back_background=”#828282″ class=”” id=””]
悩みがある方
|||
[/ms_flip_box]
[/ms_column]
[ms_column style=”1/3″ class=”” id=””]
[ms_flip_box direction=”vertical” front_paddings=”20″ front_background=”#bababa” back_paddings=”20″ back_background=”#828282″ class=”” id=””]
必要に応じて
|||
[/ms_flip_box]
[/ms_column][/ms_row]
相談予約はこちらから